はじめに
本章では、退職届を郵送で提出する際の基本的な考え方とこの資料の使い方を説明します。郵送は、やむを得ない事情で会社に直接手渡しできないときに使う方法です。具体例として、出張中・転居直後・病気療養中などが挙げられます。
-
目的と読者:本資料は、郵送で退職届を出す必要がある社員とその家族、あるいは人事担当者向けです。初めて手続きする方にも分かりやすく実務とマナーを解説します。
-
注意すべき基本事項:退職届の効力や会社規定は職場ごとに異なります。郵送自体は有効ですが、届出の受理や最終的な退職日については事前に確認してください。受領確認の方法(配達記録や内容証明の利用)も章内で扱います。
-
本資料の構成:以降の章で、郵送が許されるケース、事前準備、推奨する郵送方法、実務上の細かな注意点、封筒の選び方、添え状の書き方まで順に説明します。目的に応じて該当章を参考にしてください。
退職届の郵送が可能なケースと基本ルール
いつ郵送してよいか
遠方勤務で出社が難しい、在宅勤務で上司と対面できない、病気や育児などやむを得ない事情がある場合は、会社へ退職届を郵送して差し支えありません。会社から事前に郵送を指示されたときも同様です。例:支店と本社が離れている、人事担当が出張中で受け取りが難しい場合。
法的な扱いとマナー
法的には、意思表示が書面や電子メールでも有効な場合が多いです。ただし社会人のマナーとしては、可能なら直接手渡しか事前に口頭で伝えるのが望ましいです。郵送する場合は、受領が確認できる方法を選ぶと安心です。
基本ルール(実務)
- 送付先は人事部または直属の上司のどちらか、会社の指示に従う
- 送付方法は簡易書留や配達記録付き郵便を推奨
- 退職日や退職理由は明確に記載し、控えを1部保管
- 事前に電話やメールで郵送の旨を伝えるとトラブルを防げます。
郵送は可能ですが、相手の受け取りや確認方法を整えてから行いましょう。
郵送前の事前準備と相談
退職届を郵送する前に、必ず事前に相談して意思を伝えましょう。突然の郵送は誤解やトラブルを招きます。ここでは準備と相談の進め方を分かりやすく説明します。
1. 事前の心構え
- まず上司に直接伝えることを基本とします。会社に行けない事情がある場合でも、まず連絡で意思を示してください。
- 退職日は自分の希望ですが、業務引継ぎや会社の都合も考慮して柔軟に調整する姿勢を持ちます。
- 退職届の写しを作り、手元に保管します。
2. 上司への伝え方(対面・電話・メールの順)
- 対面が可能なら、短時間でも面談を依頼して伝えます。例:「お時間を頂けますか。退職についてご相談したいです」
- 対面が難しいときは電話で丁寧に伝えます。要点を簡潔に話し、面談の希望日を出してください。
- 電子メールは補助手段とし、要点と面談希望日を明記します。件名は「退職のご相談(氏名)」など分かりやすくします。
3. 会社に赴けない理由の伝え方
- 病気や家庭の事情など理由は正直に、かつ簡潔に伝えます。長く詳述する必要はありません。
- 可能なら代替案を示します(例:郵送で提出、本人不在時の受領方法、オンライン面談等)。
4. 相談で確認すべき点
- 最終出勤日、引継ぎ方法、退職手続きの担当者、離職票や有給の扱い、貸与物の返却方法。
- 受領確認の方法(受領書やメールでの確認)も合わせて確認します。
5. トラブルを避けるための実務ポイント
- 面談や電話後は、話した内容を要約したメールを送って記録を残します。
- 上司の了承が得られたら、郵送前にその旨を再確認し、受領確認が取れる方法で送る準備をします。
事前相談を丁寧に行えば、認識のずれや余計な摩擦を減らせます。落ち着いて一つずつ確認して進めましょう。
郵送方法の選択と推奨される方法
退職届を郵送する際の方法は、目的に応じて選びます。会社が指定していなければ普通郵便でも法的に問題はありませんが、紛失や到着の有無を気にする場合は証拠を残せる方法をおすすめします。
-
普通郵便:費用が安く手軽です。到達記録や受領証を残せないため、トラブルが心配な場合は避けたほうが安全です。
-
書留:郵便物の引受けと配達を記録します。本人が受け取ったかどうかの記録が残るため、紛失・未着トラブルで有利になります。
-
内容証明郵便:差出日と文面を郵便局が証明します。退職届の内容や送付日を明確に残したいときに有効です。配達事実を示すために配達証明を付けると、到達の証拠にもなります。
-
特定記録:安価で発送記録を残せますが、受領の記録は残りません。書類の発送を証明したい場合に使えます。
利用の流れ例:文書のコピーを用意→封入し封筒に宛名を記載→郵便局窓口で書留や内容証明の手続きを依頼→受領証や控えを保管。窓口手続きは追加料金がかかりますが、後々のトラブル回避に役立ちます。
郵送時の実務的な注意点
1) 郵便窓口での料金確認を優先する
切手を貼ってポスト投函すると、料金不足で戻る・配達が遅れる可能性があります。必ず郵便局の窓口で封筒を計量してもらい、適切な料金を支払ってください。窓口では追加サービス(書留・速達・配達記録など)も同時に申し込めます。窓口で受け取る受領証は大事に保管してください。
2) 記録が残る方法で送る
退職届は受領を証明できる送付方法を選びます。おすすめは書留(簡易書留を含む)や配達記録、配達証明の組合せです。書留は追跡と受領印が残るため、後で「届いたか」を確認できます。窓口で追跡番号や受領証を受け取り、控えを保存してください。
3) 封緘と同封書類の扱い
封はしっかりと閉じ、封筒ののり付け部分に掛け紙や透明テープで補強すると安全です。重要書類は折らずに入るサイズの封筒を使うか、折り目がつかないように薄い台紙を入れて補強してください。原本を同封する場合は、自分用にコピーを必ず残しましょう。
4) 宛先・差出人の確認
宛先住所と担当者名は正確に書いてください。部署名や役職が分かる場合は併記すると親切です。差出人欄には連絡先(電話番号)も書いておくと、連絡を受けやすくなります。
5) 送付のタイミングと記録保存
郵便局で発送日が分かる受領証を受け取り、書類のコピーと一緒に保管してください。送付後は追跡番号で配達状況を確認し、問題があればすぐに郵便局や会社に連絡します。
封筒の選び方と書き方
内封筒の選び方
白色無地で郵便番号枠のない封筒を選びます。用紙を折らずに入れるなら角2(240×332mm)、A4を三つ折りにするなら長形3号(120×235mm)が適しています。窓付き封筒は避けてください。
内封筒の書き方
表面は封筒の中央よりやや上に横書きで「退職届」または「退職願」と書きます。文字は黒インクで、読みやすい太さにしてください。裏面には所属部署名と氏名を記載します(例:「営業部 山田太郎」)。のり付けして封をしたら、封の中央に「〆」と書いて封印します。
外封筒の選び方
郵便番号枠のある大きめの封筒を用います。A4を折らずに送るなら角2、折って送るなら長形3号を使います。郵送中に中身が汚れないよう厚手の封筒を選ぶと安心です。
外封筒の書き方と封入方法
表面に宛先(会社名・部署名・役職・担当者名)を明記します。宛名が会社宛てなら「御中」を、個人名が分かる時は「様」を付けます。差出人住所・氏名は左上か裏面に記載します。内封筒と添え状を入れ、きちんとのり付けして封をします。裏面中央に「〆」と押印または記入して封を閉じたことを示してください。
書き方のポイント
・文字は黒で読みやすく。手書きが正式な印象を与えます。
・宛名は正確に、役職や部署名まで忘れずに。
・重要書類なので封はしっかり、〆印で封の完了を示しましょう。
以上を守れば、封筒の見た目とマナーが整い、受け取る側にも丁寧な印象を与えます。
添え状(送付状)の作成方法
概要
退職届を郵送する際は添え状を同封します。添え状は1枚に簡潔にまとめ、送付年月日・送付先・差出人情報・タイトル・頭語・結語・挨拶文・本文・送付物の明記を記載します。受取時期の確認や担当者への説明に役立ちます。
記載項目と書き方(詳しく)
- 送付年月日:郵便を出した日を記載します。受取時の照合に役立ちます。
- 送付先:会社名と部署名、担当者の氏名を明記します。担当者不明なら役職名を書くと丁寧です。
- 差出人:自分の氏名、住所、電話番号またはメールアドレスを記載します。
- タイトル:例「退職届送付の件」など簡潔に。
- 頭語・挨拶:ビジネスマナーとして「拝啓」など短めに書きます。続けて一文で要件を伝えます。
- 本文:退職届を同封した旨、提出日(または希望日)、連絡先、受領確認のお願いを明記します。余計な感情表現は避けます。
- 送付物:封入物を箇条書きで記載(例:退職届1通)。
書き方の例(短文)
送付年月日:2025年○月○日
送付先:株式会社○○ ○○部 ○○様
差出人:住所・氏名・電話
タイトル:退職届送付の件
拝啓 平素よりお世話になっております。別紙の通り退職届をお送りいたします。ご査収のほどよろしくお願いいたします。
記載内容の確認や受領連絡があると安心です。
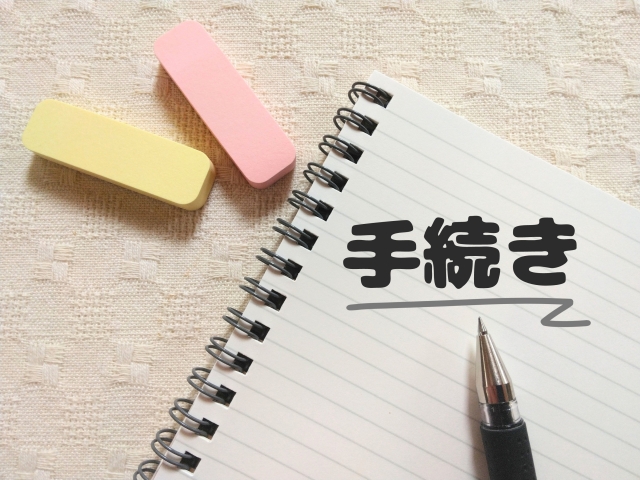









コメント