はじめに
本書の目的
本書は、源泉徴収票に記載される「乙欄」について、意味や適用条件、甲欄・丙欄との違い、税負担や実務上の注意点までを分かりやすく解説します。副業が増える中で、働き方に応じた税の扱いを正しく理解することが目的です。
対象読者
- 副業やアルバイトをしている個人
- 企業の給与担当者や人事担当者
- 源泉徴収の基礎を確認したい方
難しい専門用語は極力避け、具体例で説明します。
本書の構成と読み方
本書は全9章で構成します。第2章以降で乙欄の定義、適用ケース、税負担の違い、年末調整や確定申告での扱いなどを順に説明します。まず第2章で基礎を押さえ、その後実務的な注意点(第6章)や変更手続き(第7章)を参照すると実務で役立ちます。
使い方のポイント
手元に源泉徴収票や給与明細を用意して読み進めると理解が深まります。具体的なケースを想定しながら章を追うと、自分や自社の対応が見えてきます。
源泉徴収票の乙欄とは何か
乙欄とは
源泉徴収票の「乙欄」は、給与所得者が「扶養控除等申告書」をその勤務先に提出していない場合に用いられる区分です。乙欄に該当すると、年末調整がその勤務先では行われない扱いになります。
どう記載されるか(簡単な見分け方)
- 源泉徴収票や給与明細の区分欄に「乙」と記載される場合があります。\n- 実務上は、その勤務先が源泉徴収税額表の乙欄に基づいて税額を計算していることを意味します。
乙欄が示す具体的な意味と影響
- 扶養控除等申告書を提出していないため、扶養や配偶者控除などが考慮されません。\n- 結果として毎月の源泉徴収額が多めになります。\n- 年末調整をその勤務先では受けられないため、他に年末調整を受けていない場合は確定申告が必要になることがあります。
よくあるケース(イメージ)
- 本業で扶養控除等申告書を出しているA社があり、副業のB社に申告書を出していない場合、B社は乙欄で源泉徴収します。\n- 短期のアルバイトや単発の仕事でも乙欄扱いになることがあります。
簡単な対応方法(次章以降で詳述)
- 勤務先に扶養控除等申告書を提出するか、税務上の調整が必要なら年末に確定申告を行います。\n- 不明な点は勤務先の給与担当者に相談してください。
源泉徴収税額表の甲欄・乙欄・丙欄の違い
概要
源泉徴収税額表は甲・乙・丙の三区分に分かれ、勤務先や提出書類の有無で使い分けます。目的は給与から正しく税金を差し引くことです。
甲欄(主たる勤務先)
・扶養控除等申告書を提出した主な勤務先で使います。
・扶養や基礎控除などが反映され、差し引かれる税額が軽くなります。
・例:会社を一カ所だけ勤めている人は通常甲欄になります。
乙欄(申告未提出・副業)
・扶養控除等申告書を提出していない勤務先や、副業・掛け持ち先で使います。
・控除が反映されず、税額が高めに差し引かれます。
・例:副業の給与を受ける場合、そちらは乙欄で源泉徴収されることが多いです。
丙欄(日雇い等短期)
・日雇いや臨時の短期労働者向けです。
・扱いが簡便で、別の税率や計算方法が適用されることがあります。
比較のポイント(実務上の目安)
・誰が対象か:甲=主たる勤務先、乙=申告未提出・副業、丙=日雇い等。
・控除の有無:甲のみ控除が反映される点が大きな違いです。
・対応方法:複数勤務がある場合は主たる勤務先に扶養控除等申告書を提出すると、他は乙欄でも年末調整や確定申告で調整できます。
章内での詳しい手続きや注意点は次章で説明します。
乙欄が適用される具体的なケース
概要
乙欄は、給与を支払う側へ「給与所得者の扶養控除等(申告書)」を提出していない場合などに適用されます。ここでは代表的なケースを具体例で説明します。
ケース1:副業・掛け持ちの勤務先
主たる勤務先で申告書を提出していると、副業や掛け持ちの職場は乙欄になります。例:Aさんは会社Aを主に働き、会社Bで週末だけ働く場合、会社Bは乙欄で源泉徴収します。
ケース2:短期雇用・アルバイト
短期間の仕事や単発アルバイトでは、 employerに申告書を提出しないことが多く、乙欄が使われます。例:夏休みのアルバイトで勤務先へ書類を出していなければ、乙欄で税が引かれます。
ケース3:申告書を未提出の場合
新しく入った職場で申告書を出し忘れた、または提出時期が合わなかった場合、最初から乙欄での源泉徴収になります。早めに提出すれば次月から甲欄に変わることがあります。
ケース4:企業側の手続きミス
雇用側の管理ミスや書類の紛失で乙欄扱いになることがあります。例:人事が申告書を受け取っていても登録ミスで乙欄になることがあるので、給与明細で確認してください。
見つけたときの対応
乙欄に気付いたら、まず勤務先へ申告書を提出するか、ミスなら訂正を依頼してください。甲欄に戻せない場合でも、年末調整や確定申告で過払い分が還付されることが多いです。
乙欄適用時の税負担と控除
概要
乙欄が適用されると、給与の源泉徴収で基礎控除や配偶者控除、扶養控除が反映されません。結果として甲欄より毎月の天引きが多くなります。年収は変わらなくても手取りが少なく感じることが多いです。
控除が適用されない点
- 基礎控除・配偶者控除・扶養控除が源泉段階で引かれません。
- 社会保険料や生命保険料控除などの一部控除も年末調整や確定申告でしか反映されません。
同じ給与でも差が出る具体例
例えば月給20万円の場合、甲欄の会社で扶養申告を出していれば源泉は抑えられます。乙欄だと控除が入らないため、数千円〜数万円単位で差が出ることがあります。差額は家計に影響するので注意してください。
賞与に対する扱い
乙欄であっても賞与(ボーナス)には一律20.42%の源泉徴収率が適用されます。賞与では控除の有無にかかわらず同率で天引きされます。
税負担を軽くする方法(簡単な対処)
- 主たる給与先に「扶養控除等(異動)申告書」を提出すれば甲欄に戻せる場合があります。
- 年末調整や確定申告で過不足を精算できます。特に医療費や保険料の控除がある方は申告を検討してください。
日常の手取り差を理解し、必要なら勤務先や税務署に相談して手続きを確認すると安心です。
乙欄記載時の注意点と実務リスク
注意点
- 乙欄は一時的な区分です。扶養控除等申告書や必要書類の未提出で適用されます。書類の案内や回収を怠ると、従業員に予期せぬ税負担が生じます。
主な実務リスク
- 給与計算ミス:データ入力や区分選択の誤りで乙欄が適用されると源泉徴収額が増えます。
- 労務トラブル:従業員が差額の返還や説明を求めることが増えます。
- 年末調整の負担:乙欄の人は原則として本人が確定申告で調整する必要があります。会社側での年末調整対象にならない点に注意してください。
- 転職時の扱い:乙欄の源泉徴収票は従業員本人に返却され、転職先では年末調整されません。転職先に正しく伝わらないと二重の手続きミスが起きます。
具体例
- 例1:扶養申告書を回収し忘れ、ひと月のみ乙欄が適用。従業員が翌年確定申告で手続きを行う必要に。
- 例2:給与システム設定ミスで全員乙欄適用。大量の訂正と従業員対応が発生。
対処と予防策(実務チェックリスト)
- 入社時と年始に書類回収のリマインドを行う。
- 給与システムで区分入力欄を必須にする。
- 乙欄が付いた場合は速やかに本人へ説明し、必要書類の提出を促す。
- 訂正が必要なときは源泉徴収票の再発行、社内での履歴保存、税務署や税理士への相談を行う。
社内運用ポイント
- 担当者が変更されても対応できるよう、手順書を整備してください。内部チェックを複数段階にするとミスを減らせます。
乙欄から甲欄・丙欄への変更と対応方法
勤務先や雇用形態の変更で、源泉徴収の欄(乙欄・甲欄・丙欄)が変わることがあります。ここでは代表的なケースと実務的な対応をやさしく説明します。
1. まず確認すること
- 現在どの欄で源泉徴収されているかを給与明細や源泉徴収票で確認します。
- 他に勤務先があり、そこに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出していないか確認してください。甲欄にできるのは原則ひとつの勤務先だけです。
2. 乙欄→甲欄にする方法
- 新しい勤務先を主たる給与先にする場合は、その勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。
- 申告書を出すと、以後は甲欄で源泉徴収されます(給与計算のタイミングによっては翌月から反映することがあります)。
3. 甲欄→乙欄になる場合と対応
- 副業を始めるなどで、すでに甲欄で申告している会社以外で給与をもらうと、その副業先は通常乙欄で源泉徴収します。
- 間違いで甲欄が適用されている場合は、勤務先の総務・給与担当に連絡し、申告書の提出状況を確認して修正を依頼してください。
4. 丙欄(日雇い)→甲欄・乙欄への変更
- 日雇い労働などで丙欄になっている場合、同じ職場で通常の雇用契約に変われば、扶養控除等申告書を提出して甲欄にするか、副業扱いなら乙欄のままになります。
5. 実務上の注意点
- 申告書のコピーは必ず保管してください。
- 変更の反映は給与計算のタイミングで異なります。過払いがあれば年末調整や確定申告で精算できます。
- 不明点は早めに勤務先の給与担当や税務署に相談してください。
乙欄適用時の年末調整・確定申告
概要
乙欄で源泉徴収された給与は、原則として勤務先で年末調整されません。本人が確定申告を行い、1年間の所得や控除をまとめて税額を精算する必要があります。
なぜ確定申告が必要か
乙欄は源泉税が多めに徴収される仕組みです。そのため年末調整が行われないまま年末を迎えると、過不足がそのまま残ります。確定申告で実際の税額を計算し、過払い分の還付申請をします。
還付が見込める具体例
例えば給与から多めに税が引かれている場合、医療費控除や社会保険料控除、配偶者控除などを申告すると還付されることがあります。
退職後の取扱い
退職後に発行される乙欄の源泉徴収票は、転職先で年末調整に使えません。自分で確定申告を行う必要があります。
確定申告の手順と必要書類
用意する主な書類は源泉徴収票、各種控除の証明書(生命保険料、社会保険料、医療費の領収書など)です。申告は税務署窓口、郵送、またはe-Taxで行えます。期限は原則として翌年の3月15日までです。
実務上の注意点
源泉徴収票は大切に保管してください。還付申告を忘れると過払いが戻りません。不安な場合は税務署や税理士に相談すると安心です。
よくある質問と実務担当者向けアドバイス
源泉徴収票の交付時期
- 退職者へは退職時に源泉徴収票を交付します。定期雇用者は年末調整後に翌年1月中に渡すのが一般的です。早めに準備し、本人確認と送付記録を残してください。
乙欄のまま退職した場合の処理
- 所得税が多めに差し引かれていることが多いです。退職時の源泉徴収票で差額を確認し、必要なら確定申告で還付申請を案内します。手続きの流れを簡潔に説明する書面を添えると親切です。
申告書管理と案内のポイント
- 給与支払報告や扶養控除等申告書の提出状況をデータで管理します。提出漏れがある場合は速やかに督促し、乙欄適用の理由を本人に明確に伝えましょう。案内文は具体例(提出期限、必要書類)を入れてください。
乙欄適用時の確定申告の流れ
- 源泉徴収票を用意する。2. 給与所得の計算と必要控除を確認する。3. 還付がある場合は確定申告書を提出する。税務署やe-Taxの利用方法も案内します。
実務担当者へのチェックリスト
- 扶養控除申告書の有無確認
- 源泉徴収区分(甲・乙・丙)を記録
- 退職者への源泉徴収票交付と送付記録
- 確定申告の案内文テンプレートの準備
ミスを防ぐためのアドバイス
- 書類は受領印や電子ログで証跡を残す。ルールを社内マニュアル化して新人にも分かる手順を用意します。還付手続きについては、本人の同意を得た上で案内し、必要書類をチェックリスト化してください。
よくある質問(Q&A)
Q: 乙欄のままでも還付は受けられますか?
A: はい。源泉徴収で多く引かれていれば、確定申告で還付を受けられます。
Q: 申告書を出さない社員がいる場合は?
A: 提出を促し、提出がない旨と税区分の影響を個別に説明してください。
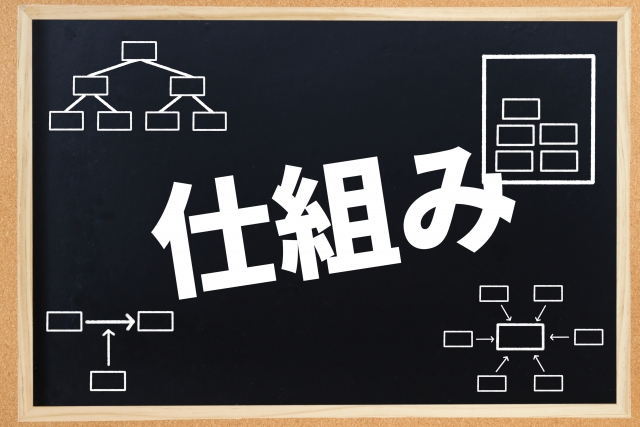









コメント