はじめに
本記事では、企業や公務員の就業規則における「病気休暇(病休)」について、制度の内容から運用上の注意点までわかりやすく解説します。
病気休暇は法律で義務づけられている制度ではなく、企業ごとに設計が異なります。たとえば、年次有給とは別に一定日数を認める会社、短期のみを扱う会社など様々です。具体例を交えて、取得条件や日数、給料の扱い、休職との違いを丁寧に説明します。
本稿は、労務担当者、人事担当者、管理職、働く方本人がそれぞれ実務で迷わないように作成しました。就業規則を作る・見直す際のポイントやトラブルを防ぐための記載例も紹介しますので、自社の制度検討や職場での相談にお役立てください。
章立てに沿って順に読み進められます。具体的な運用例や書き方を見ながら、自社の実情に合った制度設計を考えてみてください。必要に応じて、労務の専門家や労働基準監督署にもご相談ください。
病気休暇とは何か
概要
病気休暇(病休)は、業務以外の病気やけがで働けない従業員が、心身の回復や治療に専念するために取得する特別な休暇です。インフルエンザや手術後、精神的な不調など、理由はさまざまですが、目的は業務復帰のための休養です。
特徴
- 法定の制度ではなく、導入の有無や日数、給与の扱いは企業ごとに決まります。公務員は別に規定があります。
- 連続して取る場合と分割して取る場合があります。
- 医師の診断書を求める会社が多いです。
対象と適用範囲
正社員だけでなく、契約社員やパートにも適用するかは就業規則で定めます。適用範囲は明確にしておくとトラブルを防げます。
手続きの流れ(主な例)
- 発症や受診をしたら速やかに上司へ連絡する。
- 医師の診断を受け、必要なら診断書を提出する。
- 会社に休暇を申請する。復職時は報告や復職診断が求められる場合があります。
目的と職場の配慮
病気休暇は従業員の回復と安全な職場復帰が目的です。職場は代替業務や業務調整、産業医や人事による支援を用意すると安心です。
注意点
給与や手当の支給は会社規定によります。長期化する場合は休職制度や公的な傷病手当金などの利用を検討してください。
病気休暇と休職との違い
定義の違い
病気休暇は短期間の療養を目的とした特別休暇です。通常、回復が見込める場合に数日〜数週間の範囲で取ります。休職は長期間の就労不能に対応する制度で、数ヶ月〜数年にわたる場合があります。
目的と期間の目安
病気休暇は回復して職場復帰することを前提にします。たとえば風邪や軽いケガで数日休むケースです。休職は長期治療や療養、家庭の事情で長く働けないときに使います。
給与・待遇の違い
病気休暇は有給と無給が企業ごとに分かれます。有給であれば通常の給与が支払われます。休職中の給与は就業規則で定められ、無給となることが多いです。社会保険や傷病手当金の関係も確認が必要です。
手続きと証明書類
どちらも医師の診断書を求められることが多いです。病気休暇は比較的簡単な申請で済みますが、休職は届出や期間の合意、就業規則に基づく手続きが必要です。
実務上のポイント(例)
- まず病気休暇で様子を見る。回復しなければ休職へ移行する流れを定める。
- 復職時の診断書や職場調整について事前にルールを作る。
- 給与の扱いや福利厚生の継続などを明確にしておくとトラブルを防げます。
病気休暇の取得条件と日数
対象となる傷病
病気休暇は業務外に生じた私的な病気やけがを対象にします。業務に起因する場合は労災保険の対象となり、病気休暇と区別されます。日常的な通院や療養が必要な場合に使う制度と考えてください。
取得日数の決め方
取得できる日数や有給か無給かは各企業の就業規則で定めます。企業は勤務形態や業務の影響を考えて上限や単位を決めます。短時間勤務が多い場合は時間単位での取得を認めることが多いです。公務員は連続90日まで有給で取れる規定があります。
具体的な運用例
- 年間7日間の病気休暇(有給)
- 年間10日まで有給、それを超えると無給
- 半日・1時間単位で取得可能
- 長期療養は別制度(休職や傷病手当)へ移行
取得手続きと注意点
事前届出や医師の診断書を求める会社があります。急な発熱など緊急時はまず上司や人事に連絡してください。就業規則に明記がない場合は労使で運用ルールを確認すると安心です。
病気休暇中の給料の扱い
概要
病気休暇中の給与支払いは、会社の就業規則や規定で決まります。民間企業に法律上の有給義務はなく、有給と無給の両方があり得ます。一方、公務員は法律や条例で一定期間の支給が定められている場合が多いです。
民間企業での扱い(例付き)
会社が有給扱いと定めれば通常の給与が支払われます。例えば「年次病気休暇5日までは給与支給、それ以降は無給」という規定がある会社もあります。無給の場合は給与が発生しませんので、事前に就業規則や人事に確認してください。
公務員の場合
多くの自治体・機関では初めの90日程度は満額支給とする規定があります。90日を超えると減額や休職扱いになることがあるため、所属先の規定を確認してください。
公的給付との関係(傷病手当金など)
健康保険の傷病手当金は、会社から給与が出ないときに受けられる場合があります。一般に条件は療養のため労務不能であること、連続した待期期間などが必要で、支給額は標準報酬日額の約2/3、支給期間には上限があります。
手続きと注意点
就業規則、雇用契約、給与規程をまず確認し、医師の診断書や申請書類を早めに提出してください。年次有給休暇との併用、社会保険の適用要件も忘れず相談しましょう。
病気休暇の導入状況と実態
調査結果のポイント
厚生労働省の調査では、病気休暇を導入する企業は全体の21.9%にとどまります。従業員1,000人以上の大企業では37.9%ですが、中小企業では18.4%と低く、規模で差が出ています。制度があるかどうか、また内容は企業ごとに大きく異なります。
大企業と中小企業の違い
大企業は制度設計や財務面、人員の余裕から導入しやすい傾向です。中小企業は人手不足やコストを理由に導入を見送ることが多く、個別の対応で済ませる場合があります。たとえば、インフルエンザで1週間休む社員に対し、就業規則で有給か無給かを明確にしないまま対応することがあります。
導入が進まない主な理由
主な理由は次の通りです。
– 人手不足で代替要員を確保しづらい
– 給与支払いなどコスト負担への懸念
– 就業規則や運用ルールの整備が負担
これらに加え、病気休暇の運用方法が不明確で現場判断に頼る場面が多いことも要因です。
企業が取り組む際の実務ポイント
- 就業規則で制度の有無・日数・給与扱いを明確にする
- 休暇申請から復帰までのフローを決める(例:医師の診断書の扱い)
- 周知を徹底し、上司や人事が一貫した対応を取る
小さく始めて運用を改善することで導入の負担を下げられます。
導入のための簡単な一歩
まずは就業規則に「病気休暇に関する基本方針」を加え、短期の有給扱いや診断書要否などを試験的に定める方法が現実的です。運用で問題が出たら都度見直していくと無理なく定着します。
就業規則への記載例・運用ポイント
趣旨
病気休暇は、従業員が疾病や傷害により療養や治療を受けるための休暇です。就業規則では目的と適用範囲を明確にします。
取得事由・付与日数
- 対象:業務外の疾病・負傷による療養
- 付与例:年次で5日(繰越不可)や、連続休養が必要な場合は別途上限を設ける等、具体日数を定めます。
有給・無給の扱い
- 有給とするか無給とするかを明確に記載します。給与支給の判断を別規定とする場合はその旨を明記します。
手続き(診断書等)
- 申請方法:事前に上司へ連絡し、所定の申請書を提出
- 診断書:休暇開始から○日以上または連続休暇が○日を超える場合に提出を求める、といった具体的基準を示します。
- 提出期限や費用負担(原則本人負担など)も明記します。
運用ポイント
- 周知:就業規則と社内案内で周知し、質問窓口を設けます。
- 個人情報保護:診断書等の情報は機密扱いとし、閲覧者を限定します。
- フロー整備:申請→承認→勤怠処理→給与処理の流れを定めます。
- 柔軟な対応:重篤ケースやリハビリ中の部分勤務など個別対応ルールを準備します。
- 専門家相談:曖昧な点は労務専門家や弁護士に相談して規定化します。
記載例(例文)
「病気休暇は、従業員が疾病又は負傷により療養を要する場合に付与する。付与日数は年間5日とする。休暇が3日を超える場合は医師の診断書の提出を求める。給料の扱いは別途給与規程による。」
不明確な記載はトラブルにつながりやすいので、実務フローと合わせて具体化してください。
注意点・その他
不利益な取り扱いの禁止
病気休暇を理由に解雇や減給、昇進の差し控えなど不利益な処分を行うと無効となる場合があります。例えば、長期の病気休暇取得を理由に雇用契約を解除した場合、合理的な理由や手続きがなければ無効となる可能性があります。社内で扱う際は公平性を重視してください。
解雇前の手続き(休職制度の適用)
解雇を検討する前に、まず就業規則に基づく休職制度の適用を検討します。就業規則に休職の条件や期間が定められている場合、そちらを先に適用する必要があります。手続きを踏まずに解雇すると法的争いになるリスクが高まります。
他の特別休暇との違い
生理休暇や特定疾病休暇(例:がん治療休暇など)は目的や給付条件が異なります。たとえば生理休暇は短期間の休養を想定し、特定疾病休暇は治療や通院のために長期化することがあります。病気休暇との区別を就業規則で明確にしてください。
プライバシーと情報管理
病気の内容は機微情報です。診断書や申請書類は必要最小限に留め、保存や閲覧の権限を限定してください。社員の同意なく情報を公表しないでください。
実務上のポイント
申請方法(口頭・書面)、診断書の要否、給与取り扱い、復職時の職務調整や段階的復帰の方針を明示しておくと混乱を防げます。例えば医師の指示に合わせて短時間勤務から始めるルールを設けるとよいです。
相談窓口と定期見直し
労務担当や産業医、人事相談窓口を明確にし、運用状況を定期的に見直してください。運用の中で問題が見つかれば就業規則や運用フローを改善すると安心です。
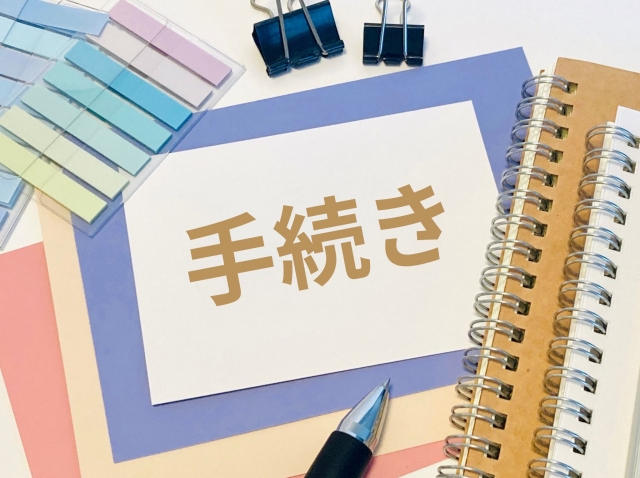









コメント