はじめに
退職を決めた後に、退職日まで出社せず欠勤したいと考える方は少なくありません。本章では、そうした状況で何を考え、どのように進めればよいかの全体像をやさしく説明します。
本記事の目的
- 心身の不調や家庭の事情で出社が難しい場合に、トラブルを避けつつ会社へ意思を伝える方法を示します。
- 法的・実務的なポイント、具体的な連絡例、退職代行サービスの活用法、リスク回避の注意点を分かりやすくまとめます。
読んでほしい方
- 退職を決めたが出社がつらく欠勤したい方
- 会社とのやり取りに不安がある方
- 家族や治療の都合で出社が難しい方
進め方と注意点
本記事は専門用語を少なく具体例で説明します。ただし、会社の就業規則や雇用契約、労働法の適用は個別に異なります。必要に応じて労働相談窓口や弁護士に相談してください。
次章以降で、具体的な手続きや連絡文の例、退職代行の使い方などを順に解説していきます。
退職日まで欠勤は可能か?法的・実務的ポイント
法的なポイント
民法627条により、期間の定めのない雇用契約は2週間前に申し出れば退職できます。つまり、法的には短期間の予告で退職できます。退職日までの勤務義務は残るため、有給休暇を使えば出勤せずに過ごせます。有給がない場合は欠勤扱いになります。
実務的なポイント
会社が同意すれば即日退職や退職日までの欠勤を認めてもらえます。まず就業規則や雇用契約書で、欠勤や無断欠勤に関する規定を確認してください。就業規則に「無断欠勤が懲戒や退職理由になる」とある場合があります。
具体的な対応例
- 有給が残っている:有給消化を申し出て、退職日まで出勤しない。書面やメールで記録を残す。
- 有給がない:欠勤扱いになる可能性があるので、欠勤の理由と期間を明確に伝え、会社の同意を得る。医師の診断書があると認められやすいです。
注意点と実務アドバイス
給与の扱いや社会保険の手続きでずれが出ることがあります。口頭だけで済ませず、退職日や欠勤扱いについて書面(メール可)で確認してください。就業規則に疑問がある場合は人事や労基署に相談すると安心です。
欠勤のまま退職する場合の伝え方・連絡方法
はじめに
欠勤のまま退職する場合は、単に「休みます」と伝えるだけでなく、退職の意思も合わせて明確に伝えると安心です。理由を丁寧かつ具体的に伝え、可能なら書面で記録を残します。
誰に伝えるか
まずは直属の上司に電話で連絡します。上司と連絡が取れない場合は人事部や総務に連絡します。小さな職場では代表者へ直接伝えます。
連絡手段の使い分け
- 電話:急ぎや説明が必要なときに向きます。相手の反応も確認できます。
- メール:記録を残したいときに必須です。電話の後にメールで要点を送ると安心です。
- チャット/メッセージ:普段の連絡手段で使っている場合は可ですが、正式な退職意思はメールで残してください。
伝えるときのポイント
- 具体的な期間や最終出勤日を伝える(例:「退職日まで欠勤します」)。
- 理由は簡潔に述べ、必要なら診断書を提出する旨を伝える(体調不良や精神的理由の場合)。
- 引き継ぎや会社からの連絡方法(電話・メール可否)を伝える。
- 返事や手続きの確認を依頼する。
例文
電話:
「私、○○は体調不良のため、本日から退職日まで欠勤させていただきたく思います。退職の意思も固まっております。手続きや書類についてご指示をいただけますでしょうか」
メール:
件名:退職のご連絡(欠勤扱い)
本文:本日より体調不良により退職日まで欠勤させていただきたく、ご連絡します。診断書は添付します。手続きや引き継ぎのご指示をお願い申し上げます。
困難な場合は第三者に依頼する選択肢もあります。まずは冷静に、相手が確認できる方法で伝えてください。
退職代行サービスの活用
概要
会社と直接やり取りするのが難しい場合、退職代行サービスを利用すると代理で退職の意思を伝えられます。即日退職や欠勤扱いの相談にも対応する業者が多いです。
業者と弁護士の違い
業者は手続き代行に強みがあり、連絡や交渉を代行します。弁護士は法的拘束力のある対応が可能で、未払残業代やトラブルがある場合に安心です。簡単な退職なら業者、争いが予想される場合は弁護士が向きます。
利用のメリット
- 精神的負担を軽くできる
- 連絡を業者に任せ即日対応が期待できる
- 書面や記録を残してもらえることが多い
注意点
- 業者は法律行為に制限があるため、法的解決は難しい場合があります
- 会社側との関係は悪化する可能性があります
- 料金や契約内容を事前に確認してください
利用の流れ・準備
- 無料相談で状況を伝える
- 本契約・費用の確認
- 業者が会社へ連絡し退職手続きを進める
必要書類は本人確認書類と雇用契約書のコピーがあるとスムーズです。
費用の目安と相談のポイント
費用は業者で数万円〜、弁護士は高めです。必ず見積もりを取り、対応範囲(欠勤扱い、即日退職、未払い請求対応など)を確認してください。
欠勤のリスクと注意点
無断欠勤のリスク
連絡なしで休むと、解雇や懲戒の対象になりやすいです。会社は規律を重視するため、出勤義務を果たさない行為を重く見ることがあります。給与の支払いや賞与、退職金の扱いに影響することもあります。
連絡と記録を必ず残す
まず会社に連絡を入れてください。メールやショートメッセージ、電話の通話履歴など、連絡した証拠を残すと安心です。具体例:上司にメールで欠勤理由と復帰予定を伝え、送信履歴を保存します。
長期欠勤が及ぼす影響
欠勤が長期化すると会社都合退職や自然退職と判断される場合があります。雇用保険や社会保険の資格、失業給付の手続きに影響が出ることがあります。医療上の理由がある場合は診断書を用意してください。
就業規則と義務
欠勤期間中も就業規則は適用されます。引継ぎや必要書類の提出は、可能な範囲で協力する姿勢を示すとトラブルを避けやすくなります。
証拠と具体的な手続き例
・欠勤の連絡はメールで行い、送信済み画面を保存する
・電話連絡は日時と相手をメモする
・病気の場合は診断書や領収書を保管する
トラブル回避のためにできること
まず冷静に連絡を続け、記録を残してください。会社と話がこじれた場合は、労働相談窓口や弁護士に相談する選択肢もあります。引継ぎが難しいときは代理で対応できる人を提案すると良いです。
欠勤理由の伝え方・例文
伝えるときの基本
欠勤理由は具体的で事実に基づく表現を使います。相手に誤解を与えないよう簡潔に伝え、退職予定がある場合は退職日までの対応方法も合わせて伝えます。
よく使う理由と一言例
- 体調不良:発熱や嘔吐など、具体的な症状を伝えます。
- 心身の不調:通院や治療が必要な旨を伝えます(詳細は医師に留めても差し支えありません)。
- 家庭の事情:介護や子どもの急な事情など、期間の見通しを伝えます。
電話での例文(短め)
1) 体調不良
「おはようございます。○○です。今朝から高熱と吐き気があり出勤が難しいため、本日は欠勤させてください。回復次第ご連絡します。」
2) 心身の不調
「お疲れさまです。○○です。現在通院が必要な状態で安静が必要なため、数日欠勤させていただきたいです。業務の引き継ぎはメールで対応します。」
3) 家庭の事情
「お世話になります。○○です。家族の急用で本日対応が必要になりました。誠に申し訳ありませんが欠勤させてください。連絡は携帯で取れます。」
メール・文書の例
件名:「欠勤のご連絡(○○ ○○)」
本文:「お疲れさまです。○○です。本日、体調不良のため欠勤いたします。復帰の見込みは○日頃を予定しております。業務については△△が対応します。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。」
伝える時の注意点
- 事実に基づき誠実に伝えてください。必要に応じて診断書や証明を求められます。
- 退職まで欠勤する旨を伝える場合は、退職日や引き継ぎ方法も明確にします。
- 連絡手段(電話/メール/代理連絡)を予め示すと相手が安心します。
退職日までの流れと会社側の対応
欠勤扱いと在籍
会社は欠勤期間中も社員を在籍扱いにします。給与や社会保険、雇用保険の手続きは通常通り続きます。欠勤が有給か無給かは就業規則や会社との合意で決まります。
給与・保険の処理
給与は欠勤日数に応じて計算されます。社会保険料や雇用保険の事務は会社が行いますので、保険資格の喪失や手続き時期は会社から案内があります。
連絡と安否確認
長期欠勤になると会社は電話やメールで安否確認を行います。連絡が取れない場合、書面での確認や面談を求められることがあります。
長期欠勤と解雇の可能性
理由なく長期間欠勤すると懲戒や解雇の対象になることがあります。退職の意思がある場合は書面で伝え、退職日を合意すると円満に進みやすくなります。
実務上の流れ(チェックリスト)
- 退職意思を口頭と書面で伝える
- 最終出勤日・退職日を確認
- 有給消化や給与精算の方法を確認
- 保険・年金の手続き時期を把握
- 会社からの書類は保管する
会社側は手続きを進めますが、こちらからも積極的に確認するとトラブルを防げます。
まとめ
大切なポイント
退職日まで欠勤する場合は、まず会社に必ず連絡し、退職の意思と欠勤の理由を丁寧に伝えてください。口頭が難しいときはメールや書面で残すと後のトラブルを避けやすくなります。
連絡と証拠の保管
連絡日時や内容はメモや送受信履歴で保存しましょう。診断書などの証拠がある場合はコピーを取っておきます。これにより誤解や不当な扱いに備えられます。
代行サービスの活用
直接伝えづらいときは退職代行サービスを検討できます。利用前に費用や対応範囲を確認し、信頼できる業者を選んでください。
就業規則と引継ぎ
欠勤中でも就業規則は守る必要があります。可能な範囲で引継ぎや重要な連絡を行い、未処理の業務は明示しておくと良いです。
トラブル回避のチェックリスト
- 退職意思の明確化
- 連絡内容の記録
- 診断書や証拠の保管
- 代行利用の検討と確認
- 引継ぎ事項の整理
上記を押さえることで、円滑に退職手続きを進めやすくなります。丁寧な連絡と記録が最も重要です。
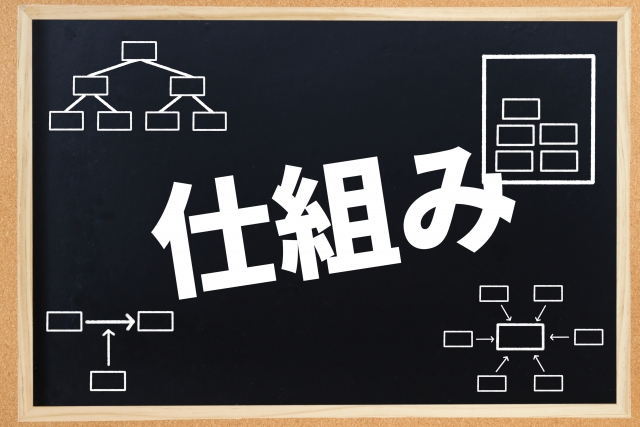









コメント