はじめに
「源泉徴収票 非課税の場合」について知りたいと感じていませんか?
この資料は、所得税が非課税になる条件や、源泉徴収票でそれを確認する方法をわかりやすくまとめています。非課税世帯の定義や基準、源泉徴収票の見方、非課税扱いになる手当や控除の取り扱い、源泉徴収票が発行されないケース、そして給与支払報告書との違いまで、実務でよくある疑問に丁寧に答えます。
対象は、会社員やパート・アルバイトの方、年末調整や住民税の手続きを行う方、また家族のために書類を確認する方です。専門知識がなくても理解できるように、具体例を交えて説明します。
この第1章では、全体の構成と本資料の使い方を示します。各章は独立して読めますので、確認したい項目から読み進めてください。必要に応じて、実際の源泉徴収票と照らし合わせながら確認していくことをおすすめします。
非課税世帯の定義とその基準
非課税世帯とは
非課税世帯とは、所得税が課されない世帯のことを指します。給与所得者の場合、年間の所得が一定額以下であれば課税所得がゼロになり、所得税がかかりません。
103万円の仕組み(給与所得者の場合)
給与所得者は給与から「給与所得控除(55万円)」と「基礎控除(48万円)」を差し引けます。これらの合計が103万円になるため、年間給与が103万円以下なら課税所得はゼロになります。例:年間給与100万円→100−55−48=−3(課税所得0)です。
母子家庭や配偶者がいる場合の違い
母子家庭(寡婦控除など)や配偶者がいる場合は、追加の控除や扶養控除が適用されることがあります。控除の種類によっては非課税となる基準が変わるため、該当する控除の有無を確認してください。
個人事業主(自営業者)の場合
自営業者は売上から必要経費を差し引いた「所得」に対して控除が適用されます。給与所得の55万円とは性質が異なるため、年間収入が103万円以下でも経費の状況によって課税されることがあります。事業所得の計算方法を確認してください。
確認ポイント
- 給与所得者か自営業かで基準が異なる
- 控除の種類(扶養・配偶者・寡婦など)で非課税の範囲が変わる
- 住民税など別の税で基準が異なる場合がある
まずは自分の収入形態と受けられる控除を整理して、課税されるかどうかを確認しましょう。
源泉徴収票で非課税を確認する方法
1. 源泉徴収票のどこを確認するか
源泉徴収票には、主に「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」が記載されています。まずこれらの欄の数字を見つけてください。欄の名称は用紙によって多少位置が異なることがありますが、見出しで探せます。
2. 非課税かどうかを判断する手順(簡単な計算)
- 「給与所得控除後の金額」を確認します。これは給与から給与所得控除を差し引いた金額です。
- 「所得控除の額の合計額」を確認します。基礎控除や扶養控除などの合計です。
- 給与所得控除後の金額−所得控除の額の合計額を計算します。結果がゼロ以下(マイナス含む)であれば、課税される所得がないため所得税は非課税になります。
3. 具体例
例:給与所得控除後の金額が43万円、所得控除の額の合計額が48万円の場合。
計算:43万円−48万円=−5万円 → 課税対象の所得は無く、所得税はかかりません。実務ではマイナスは0と扱い、税額は発生しません。
4. 注意点と確認のコツ
- 「支払金額」は手取りではなく支給総額です。控除前の金額を確認してください。
- 所得控除の合計に保険料控除や配偶者控除などが含まれているか確認してください。
- 数字に不明点がある場合は、勤務先の給与担当者や最寄りの税務署に確認すると安心です。
源泉徴収票が不要・発行されない場合
概要
給与が月88,000円未満など、一定の条件では源泉徴収が不要になる場合があります。また、業務委託などの報酬や料金として支払われる場合、源泉徴収票は発行されず、代わりに支払調書が作成されることが多いです。本章では、どんなときに源泉徴収票が不要・発行されないか、そしてその際にどう対応すればよいかをわかりやすく説明します。
給与が少額で源泉徴収がない場合
給与が月88,000円未満など少額の支払いでは、所得税の源泉徴収が行われないことがあります。具体的な金額や判断は支払いの頻度や雇用形態で変わるため、まずは給与明細や雇用契約書で支払形態を確認してください。源泉徴収がされていない場合でも、年末調整や確定申告で所得を申告する必要が出ることがあります。
業務委託・フリーランスの報酬の場合
業務委託や原稿料、講演料などは「報酬・料金」として扱われ、会社が発行するのは源泉徴収票ではなく支払調書です。支払調書は確定申告の際に使える重要な書類です。支払調書が手元にないときは、支払者に発行を依頼するか、自分の取引履歴(振込記録や請求書)を保存しておきましょう。
発行されないときの具体的な対応
1) 支払者に確認:まずは会社や発注元に源泉徴収票や支払調書の発行を依頼してください。2) 証拠を残す:給与明細、振込明細、請求書などを必ず保管します。3) 税務署へ相談:必要書類が揃わない場合は税務署に相談すると手続き方法を教えてもらえます。4) 確定申告で代替資料を使う:源泉徴収票がない場合でも、保存した証拠で所得を申告できます。
注意点
・支払者が書類を発行しない場合でも、受け取った所得は申告義務があります。・支払調書と源泉徴収票は用途が異なるため、どちらの書類が必要かを事前に確認してください。
非課税となる手当・控除の扱い
概要
一定額までの通勤手当や、社会通念上相当と認められる慶弔見舞金などは非課税扱いになります。これらを課税対象に含めると、源泉徴収票で示す給与等の金額や所得税額が実態とずれてしまいます。源泉徴収票作成時には非課税の有無を正確に把握することが大切です。
主な非課税手当と目安
- 通勤手当:一定額まで非課税(公共交通や距離・金額によりルールがあります)。
- 慶弔手当・見舞金:社会通念上相当と認められる範囲は非課税。
- 出張旅費の実費弁済:実費で支給し領収書等がある場合は非課税。
具体的な金額基準は法令で定められますので、会社の就業規則や税務相談で確認してください。
源泉徴収票作成時の扱い方
- 支給項目ごとに非課税か課税かを確認します。書類(支給規程・領収書・交通費明細)を整えます。
- 非課税分は給与等欄に含めず、別に管理します。誤って含めると給与等の金額が膨らみ、源泉税額が過大になり得ます。
誤って課税扱いにした場合の対応
誤記に気づいたら速やかに訂正します。給与支払報告書や源泉徴収票を訂正する手続きが必要です。税務署や市区町村への届出方法はケースにより異なるため、税務署や税理士に相談してください。
具体例(簡単なイメージ)
通勤手当が月3万円で、非課税限度が2万円の場合、差額1万円は課税扱いにします。非課税分2万円は源泉徴収票の給与等に含めない管理が必要です。
源泉徴収票と給与支払報告書の違い
概要
源泉徴収票は給与等に対する所得税の「支払証明書」で、勤務先が従業員本人に交付します。一方、給与支払報告書は勤務先が自治体に提出するもので、住民税の算出などに使われます。
目的と受け取り先の違い
- 源泉徴収票:本人に交付。確定申告や年末調整の確認、住宅ローンの手続きなどで使います。
- 給与支払報告書:自治体に提出。住民税の課税や税額通知の基礎資料になります。
記載内容と利用の違い
両者とも給与額や社会保険料の金額を記載しますが、源泉徴収票は所得税の源泉徴収額や控除額が詳しく載ります。給与支払報告書は住民税の計算用に住所・氏名など住民情報を明確に記載します。
提出・交付のタイミング
源泉徴収票は年末調整後に交付されます。給与支払報告書は翌年1月末までに自治体へ提出するのが一般的です。
具体例と注意点
源泉徴収票と給与支払報告書で金額が違う場合は勤務先に確認してください。自治体が住民税を計算するため、給与支払報告書の誤りは住民税に影響します。給与支払報告書の本人控えが欲しいときは勤務先に依頼するか、自治体で確認できます。
よくある質問・注意点
ブログをお読みいただきありがとうございます。ここでは、源泉徴収票と“非課税”に関してよく寄せられる質問と注意点を分かりやすくまとめます。
よくある質問
-
パートやアルバイトでも源泉徴収票は発行されますか?
はい。給与の支払いがある場合、勤務先は原則として源泉徴収票を発行します。短期間でも支払いがあれば受け取れます。 -
源泉徴収票だけで非課税と断定できますか?
源泉徴収票は目安として使えますが、住民税の非課税証明が必要な場面では自治体が発行する書類が正式です。 -
紛失や未発行の場合はどうすればいいですか?
まず勤務先に再発行を依頼してください。勤務先が応じない場合は給与の支払いを証明する書類(給与明細など)を用意し、市区町村や税務署に相談しましょう。
注意点
- 複数の勤務先や副業があると合算で判断されます。全ての収入を把握してください。
- 扶養や各種控除は所得金額に影響します。見た目の支払額だけで非課税か判断しないでください。
- 非課税証明が必要なときは、余裕をもって自治体に申請してください。手続きや発行に時間がかかる場合があります。
まとめ:源泉徴収票で“非課税”かどうかを正しく確認しよう
この記事のポイントを分かりやすくまとめます。
確認の基本手順
- まず非課税となる基準を把握します。所得税と住民税で基準が異なるため、確認先(税務署や自治体)を確認してください。
- 源泉徴収票の主な項目をチェックします。特に「支払金額」「給与所得控除後の金額」「所得控除の額の合計額」「源泉徴収税額」「社会保険料等の金額」を見ます。
- 課税対象額は「給与所得控除後の金額」から「所得控除の額の合計額」を引いて計算します。結果が非課税基準以下なら非課税となります。具体的な数字は管轄にご確認ください。
よくある見落とし
- 通勤手当など一部手当は一定額が非課税になることがあります。会社の明細や説明を確認してください。
- 年末調整や扶養控除の反映漏れで源泉徴収税額が違う場合があります。明細と源泉徴収票を照らし合わせてください。
問題があれば
- 数値に不明点があれば、まず勤務先の総務または給与担当に問い合わせてください。必要なら税理士や自治体窓口で確認すると安心です。
正しい確認を行うことで誤った納税や給付の受け損ねを防げます。迷ったときは早めに相談してください。
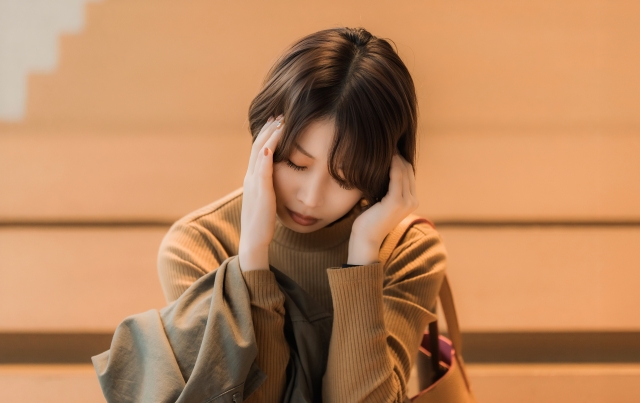









コメント