はじめに
ブログ記事をどう書けばいいかわからない……という方へ
「源泉徴収票」を見たり書いたりする機会は、多くの方にとって年に一度のことかもしれません。不安を感じるのは当然です。本章では、本書の目的と読み方、期待できる成果を分かりやすくお伝えします。
この資料の目的
この文書は、源泉徴収票の見本と正しい書き方を丁寧に解説します。基本的な役割や構造、主な記載項目の意味、記入例、作成時の注意点、効率化の方法、よくある疑問への回答まで取り上げます。
想定する読者
・会社の総務や経理担当の方
・個人事業主やフリーランスで源泉徴収票に触れる方
・初めて源泉徴収票を作る方
この章を読んで得られること
読者は、本書の全体像と利用方法を把握できます。次章以降で具体的な記載方法や見本を順を追って学べるよう設計しています。必要な箇所だけ参照して使ってください。
源泉徴収票とは?〜基本構造と役割〜
概要
源泉徴収票は、会社が従業員に年末調整後に発行する法定書類です。その年に支払った給与や賞与、各種控除、源泉徴収した所得税額を記載します。国税庁が書式を定めており、最新のフォーマットは国税庁のウェブサイトで確認できます。
発行する人と時期
- 発行者:給与を支払った事業主(会社や事業者)
- 発行時期:原則として年末調整後、翌年の1月中に渡されることが多いです。
主な記載項目(わかりやすく)
- 支払金額:その年に支払った給与や賞与の合計です。例:給与手取りではなく支給額を示します。
- 所得控除の額:社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、基礎控除などが記載されます。
- 源泉徴収税額:会社が給与から天引きして納付した所得税の合計額です。
- 支払者・受給者の情報:会社名、所在地、従業員の氏名・個人番号などが記載されます。
役割と利用場面
- 確定申告の証明書類として使います。
- 転職時の年末調整や退職手続きで提出します。
- 住宅ローンの申請など収入証明として利用します。
保管と注意点
- 大切に保管してください。再発行は手続きが必要です。
- 記載に誤りがあれば速やかに勤務先に確認・訂正を依頼してください。
源泉徴収票の見本・記載例
以下は、源泉徴収票に実際に記載される主要項目と、読み方のポイントです。実例を交えて簡潔に説明します。
対象者(受給者)情報
住所・氏名・受給者番号・役職名などが記載されます。例:田中 太郎(営業部長)、〒123-4567、東京都新宿区。
支払金額(年間給与総額)
1年間に支払った総額です。例:支払金額 4,200,000円。年収とおおむね一致します。
給与所得控除後の金額
給与所得控除を差し引いた課税対象額。例:給与所得控除後の金額 2,800,000円。
所得控除の額の合計額
社会保険料控除、生命保険料控除、扶養控除、配偶者控除などの合計。例:
– 社会保険料控除 400,000円
– 生命保険料控除 20,000円
– 扶養控除(子2人) 760,000円
– 配偶者控除 380,000円
合計 1,560,000円。
源泉徴収税額
給与から差し引かれた所得税の年間合計。例:源泉徴収税額 200,000円。
控除対象配偶者の有無・氏名、扶養親族の人数・氏名
配偶者や扶養親族の氏名と続柄、控除対象となる人数が記載されます。例:配偶者 田中 花子(有)/扶養親族 子:田中 太一、田中 花子子。
社会保険料等の金額・保険料控除
健康保険・厚生年金などの合計額が記載されます。年末調整で提出した金額と一致するか確認してください。
生命保険料控除・地震保険料控除
各保険ごとの控除額が分かれています。合計額が「所得控除の額の合計額」に反映されます。
住宅借入金等特別控除の額
住宅ローン控除がある場合は控除額が記載されます。ない場合は“0”または“—”と表示されます。
ポイント:空欄や“—”は該当なしを示します。金額に誤りがあれば早めに勤務先の総務へ確認しましょう。ご自身の年収や控除の確認に役立ててください。
記入例(見本)の具体的なサンプル
以下は実際に記入した見本の具体例です。各項目の意味と、どのように記入するかを丁寧に解説します。
- 住所又は居所:神奈川県横浜市〇〇区◇◇1-1
-
受給者の現住所を記入します。番地まで正確に書きます。
-
受給者番号:100001
-
社内や年金等で使う識別番号です。番号がある場合は記入します。
-
氏名:山田□□
-
ふりがなを併記すると親切です。
-
支払金額:4,000,000円
-
年間の支払総額(給与や報酬の合計)を記入します。
-
給与所得控除後の金額:2,760,000円
-
給与所得控除を差し引いた後の金額です。計算方法は給与額に応じて決まります。
-
所得控除の額の合計額:2,460,000円
-
各種控除(配偶者控除、扶養控除、基礎控除など)の合計です。
-
社会保険料等の金額:600,000円
-
健康保険、厚生年金、雇用保険などの本人負担分を記入します。
-
生命保険料控除額:120,000円
-
生命保険料の控除額を記入します。証明書と照合してください。
-
源泉徴収税額:42,600円
-
その年に源泉徴収された税額(控除後の税額)です。給与明細等と照合します。
-
控除対象配偶者:有(配偶者氏名記載)
-
配偶者が控除対象なら「有」と記載し、配偶者の氏名を横に書きます。
-
控除対象扶養親族の数:1(氏名記載)
- 扶養親族の人数と氏名を記入します。16歳未満など条件に注意してください。
この見本は記入のイメージをつかむための例です。実際の金額や控除の適用は個別に異なりますので、原本や計算書類と突き合わせて確認してください。疑問があればお気軽にお尋ねください。
源泉徴収票作成時の注意点・よくある疑問
記載漏れ・誤記入に注意
支払金額や源泉徴収税額、社会保険料の控除などは賃金台帳や保険料控除申告書、扶養控除等申告書をもとに正確に記載してください。通勤手当や時間外手当の扱いで漏れやすいので、明細と突合する習慣をつけると良いです。
マイナンバーの扱い
税務署提出用の様式にはマイナンバーが必要ですが、従業員に交付する用の紙には記載不要です。マイナンバーは厳重に管理し、不要になったら適切に廃棄してください。
年内に転職した場合
年内に複数の勤務先がある場合は、前職の源泉徴収票の金額を合算して記載します。従業員から前職の源泉徴収票を受け取り、年末調整や手続きで用いるようにしてください。
金額や控除の確認方法
支払金額は給与台帳、控除額は控除申告書や保険料の領収書で確認します。誤りが見つかった場合は訂正して再発行するか、必要な手続きを速やかに行ってください。
よくある疑問(Q&A)
Q: 交付期限はいつですか?
A: 翌年1月31日までに従業員へ交付する必要があります。
Q: 電子交付はできますか?
A: 従業員の同意や条件を満たせば可能です。具体的には国税庁の案内を参照してください。
最新の様式や詳細な記入例は国税庁の公式フォーマットを確認してください。
作成を効率化する方法
- 概要
パソコン入力用の様式や給与計算ソフトを使うと、手書きに比べてミスが減り作業時間を短縮できます。ここでは具体的な手順と注意点を分かりやすく説明します。
-
- 入力様式とソフトの活用
国税庁の入力用PDFや市販の給与計算ソフトを利用してください。入力欄が自動計算するため、税額や控除の計算ミスを防げます。小規模なら入力用PDF、大人数なら給与ソフトが向きます。
-
- 必要書類の事前準備
賃金台帳、雇用契約書、各種控除証明(社会保険、生命保険等)、扶養控除申告書をまとめておきます。項目ごとにチェックリストを作ると記載漏れを防げます。
-
- データの流れを決める
社員情報→月次給与→年間集計の順でデータを整理します。CSV形式でインポート・エクスポートできると、ソフト間の連携が楽になります。
-
- 確認と保存
入力後は必ず合計欄と控除欄を二重チェックしてください。PDFで保存し、原本は別フォルダにバックアップを残します。
-
- 実践の小技
テンプレートを用意して定型文や数字を自動入力する、公開日(交付日)に合わせて印刷スケジュールを組むなどで作業負担を減らせます。
まとめ・よくあるQ&A
まとめ
源泉徴収票は給与所得を証明する大切な書類です。支払金額・社会保険料・各種控除・源泉徴収税額などを国税庁の基準に沿って正しく記入します。見本や記入例を参照し、数字の合計や年号、マイナンバーの扱いに誤りがないか必ず確認してください。年末調整後に交付し、従業員や税務署の提出用に保存します。
よくあるQ&A
Q1: 発行はいつまでに必要ですか?
A1: 原則として翌年1月31日までに交付します。早めに準備すると安心です。
Q2: 間違えた場合はどうすればよいですか?
A2: 訂正が必要なら新しい源泉徴収票を作成して交付し、必要に応じて税務署へ訂正届を提出します。
Q3: 保存期間は?
A3: 帳簿書類と同様に7年間の保存が推奨されます。
Q4: 電子交付は可能ですか?
A4: 同意を得れば電子交付が可能です。保存方法やアクセス方法を明確にしましょう。
Q5: 記載項目が分からないときは?
A5: 国税庁の書式や給与計算サービスのヘルプを参照し、必要なら税理士に相談してください。
最後に、見本を元に確認とダブルチェックを行う習慣をつけるとミスを減らせます。疑問があれば具体的な状況を教えてください。
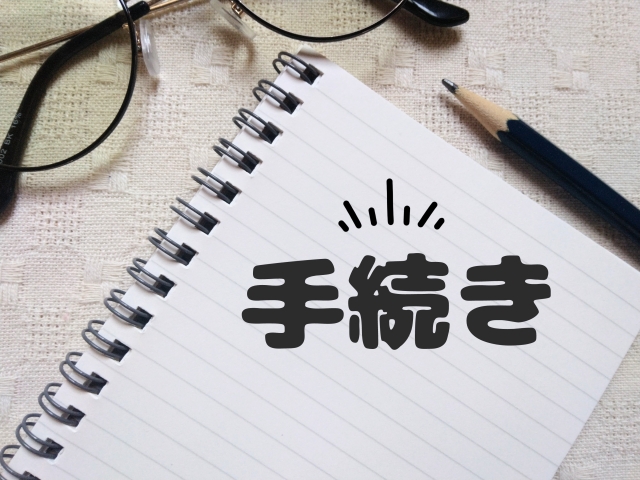









コメント