はじめに
本章の目的
本記事は、2025年時点の退職代行サービスに関する最新の利用動向を分かりやすく伝えることを目的としています。利用件数や市場規模、企業側の経験率、サービスごとの実績などを丁寧に解説します。
読者の想定
退職を考えている方、企業の人事担当者、サービス提供者、そして関心を持つ一般の方を想定しています。専門知識がなくても理解できるよう、具体例を交えて説明します。
本記事でわかること
- 退職代行サービスの利用者数や市場の大きさ
- 企業側の利用経験とその変化
- 利用が増えている背景や季節的な傾向
- 業種・企業規模ごとの違いや主要サービスの実績
読み方の案内
各章は独立して読めます。まず全体像をつかみたい方は2章から4章を、詳しい業界分析を見たい方は5章以降をお読みください。専門用語は最小限に抑え、必要な場合は具体例で補います。
退職代行サービスの利用件数と市場規模
検索数と関心の高まり
年間の検索件数は約470万回にのぼり、退職代行への関心が急速に高まっていることが分かります。求職者や在職者がまずインターネットで情報収集する例が多く、気軽に調べられる環境が利用増加につながっています。
代表サービスの実績
大手サービス「退職代行モームリ」は累計利用者数が15,934名、実際の退職代行実施件数は15,000件超(2024年時点)です。具体的な数値があることで、サービスの信頼性や利用実績を判断しやすくなっています。
市場全体の動向
個別サービスの伸びに加えて、市場全体で利用者数が年々増加しています。理由としては、直接会社と対面や電話でやり取りする負担を避けたい人が増えたこと、手続きの選択肢が増えたことなどが考えられます。
利用の際の注意点
件数や検索数は関心の高さを示しますが、サービス内容や料金、対応範囲は事業者ごとに異なります。契約前に実施の可否や追加費用、連絡方法などを確認してください。ご自身の状況に合った選択を心がけると安心です。
企業側の退職代行経験率とその推移
調査結果の要点
2024年上半期の調査では、企業の23.2%が社員の退職代行利用経験があると答えました。2019年以前の15.7%から増加しており、利用経験が広がっていることが分かります。別の調査(東京商工リサーチ)でも、大企業15.7%、中小企業6.5%と報告されており、複数の調査で同様の傾向が見えます。
規模別の違い
大企業は18.4%、中小企業は8.3%で、大企業のほうが2倍以上高い傾向が出ています。従業員数が多い企業では、単純に退職者数が多くなるため発生件数も増えやすく、外部サービスの認知度や利用しやすさも影響します。例えば社員数1000名程度の企業と50名規模の企業を比べると、相談窓口や労務担当が整備されている分、退職代行の利用が表面化しやすいと言えます。
増加の背景と考えられる要因
- 労働環境や人間関係に起因する早期離職が続いていること
- 情報発信やサービスの普及で利用方法が分かりやすくなったこと
- 人材流動化で退職手続きの外部委託が受け入れられやすくなったこと
企業が今できる対応
- 退職時の窓口を明確にし、迅速に対応する仕組みを作る
- 管理職に対して早期の面談やフォローの研修を行う
- 外部相談窓口や法的助言の連携先を用意しておく
企業側が経験率の上昇を受け止め、手続きやコミュニケーションを見直すことが重要です。
利用動向と季節変動
概要
退職・離職関連の検索は年間約1.4億回、月平均で1,000万回以上にのぼります。特に「退職届」や「退職届 書き方」は2~3月と6月に検索が増える傾向です。退職代行サービスの検索・利用は、大型連休の前後やメディア露出のあった月に急増します。
季節ごとの特徴
- 2~3月:年度末や転職のタイミングで相談や準備が増えます。辞め方の書き方や理由を調べる人が多くなります。
- 6月:上半期の区切りとして退職を決める人が目立ちます。ボーナス支給後に動く例もあります。
- 大型連休前後:休暇明けに職場の人間関係や働き方を理由に一気に相談が増えます。
退職代行の増減要因
- メディアで取り上げられると、短期間で利用や検索が集中します。
- 連休や給与支給のタイミングが心理的な引き金となりやすいです。
利用者への注意点
- 早めの情報収集が安心につながります。連休直前は混雑するため余裕を持って相談しましょう。
- 代行サービスは対応範囲や料金が会社ごとに異なります。申し込む前に確認してください。
主要退職代行サービスの利用実績
利用実績(検索数)
直近1年間の検索数を見ると、モームリが圧倒的に多く、59万5,390件でした。他の主要サービスは次の通りです。
– やめたらええねん:41,570件
– 退職代行ガーディアン:36,380件
– 退職代行exit:34,930件
– 退職代行jobs:24,510件
モームリでは1社で64回利用された事例も確認されています。
傾向と解説
検索数が多いほど必ずしも利用者が多いわけではありません。広告やSEO対策が強いと検索数が増えることがあります。ただし、モームリの高い数値と、単一企業での繰り返し利用(64回)は、実際の利用実績やミッション遂行の経験が豊富である可能性を示します。口コミやメディア露出も影響します。
選ぶときのチェックポイント
- 実績(利用件数や成功事例)
- 対応範囲(労働問題への助言や法的対応の有無)
- 料金体系と追加費用の有無
- 個別相談のしやすさと対応速度
- 利用者の声(具体的な事例や退職の満足度)
検索数は参考指標の一つです。複数の情報を照らし合わせて選ぶことをおすすめします。
退職代行利用増加の背景
退職理由と建前のギャップ
実際の退職理由と会社に伝える“建前”に差があるケースが増えています。例えば「家庭の事情」と伝えても、実際はパワハラや長時間労働が原因ということがよくあります。言いにくい事情をそのまま言うとトラブルや感情的な対立に発展することを避けたい人が増えています。
第三者を介する利点
第三者に依頼すると直接のやり取りを避けられます。感情的な言い合いや引き留めに遭うリスクを下げ、速やかに退職手続きを進められます。また、労働法や手続きの知識を持つサービスは、未払い残業や有給取得など具体的な請求を代行できます。匿名性を保てる点も安心材料になります。
情報拡散と認知の拡大
SNSやメディアで利用体験が共有され、サービスの存在と利便性が広まりました。周囲で利用した人の声を聞いて検討する層が増え、選択肢として定着しつつあります。
利用しやすさとサービスの多様化
料金体系や対応範囲が多様化し、初めてでも利用しやすくなりました。電話やチャットで完結するサービスも増え、時間的な負担を減らして依頼できる点が利用増加の一因です。
業種・企業規模別の傾向
大企業と中小企業の違い
規模が大きくなるほど退職代行の利用が相対的に増えます。従業員数が多いと離職希望者の絶対数が増え、窓口対応が追いつかないケースが出ます。大手で年間数十件単位の利用が報告されます。
業種ごとの特徴
人材派遣会社、IT企業、運送会社などで利用が多く報告されています。派遣では雇用が流動的になりやすく、ITや運送では長時間労働や不規則勤務が背景になることが多いです。これらの業種では同じ企業で複数回使われる例が目立ちます。
複数回利用の実例と要因
1社で年間60回を超える利用事例もあります。原因は職場環境の継続的な問題(人員不足、労働条件の改善遅れ、連絡体制の不備)にあることが多いです。特定職種に偏った負担が繰り返されると利用が常態化します。
企業と従業員への示唆
企業は離職のパターンを分析し、対応窓口や労務管理を整備することで再発防止に努めると良いです。従業員は利用前に相談窓口や権利を確認し、安全に退職手続きを進めると安心です。
退職代行の今後の展望
市場の見通し
2023〜2025年の増加傾向が続くと、利用者と利用経験企業はさらに増え、市場は拡大します。個人の働き方意識や転職の流動化が後押しします。
法律・制度面の整備
行政や業界団体でガイドライン整備が進みます。窓口の明確化やトラブル防止のためのルールが求められ、法的な責任範囲が明瞭になります。
サービス品質の向上
代行業者は説明責任や手続きの透明化を重視します。労働相談やメンタルケアを含めたワンストップサービスが増え、信頼性が上がります。
企業側の対応変化
企業は早期退職対策や労務管理の見直しを行います。退職理由の分析や働き方改革を進めることで、離職抑止につなげます。
利用者が注意すべき点
料金体系や対応範囲を事前確認してください。証拠保存や連絡方法を整理すると、トラブルを避けやすくなります。
技術と新しいサービス
オンライン相談やAIによる初期対応が普及します。手続きの効率化で利用の敷居が下がり、より選ばれる選択肢になります。
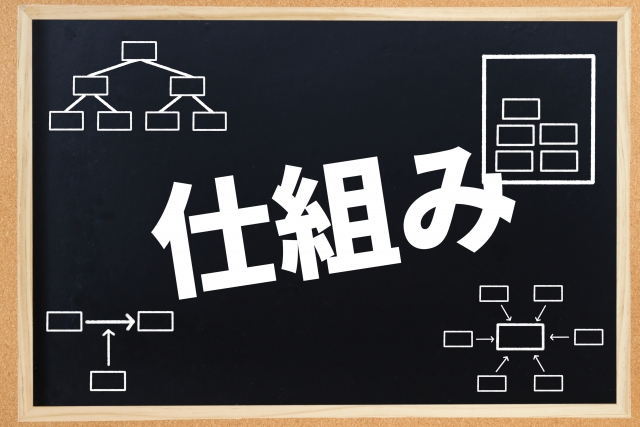









コメント