はじめに
「役員として退職を考えているが、何をどのように書けばいいか分からない」「退職届や辞表は本当に必要なのか不安だ」という疑問をお持ちではありませんか? 本記事は、会社の役員が退職する際に知っておきたい実務とマナーを、わかりやすく整理して解説します。
本記事の目的
本記事では、役員の退職届や辞表の必要性、書き方の基本、テンプレート例、提出時の注意点やマナー、そして従業員の退職届との違いまでを順に説明します。実務で使える具体例を多く載せているため、そのまま参考にできます。
誰に向けた記事か
会社の代表取締役や取締役、監査役などの役員、または役員の退職手続きを担当する総務・人事の方に役立ちます。初めて役員の退職手続きを行う方でも理解できるよう、専門用語は最小限にし、具体例で補足しています。
読み進め方の提案
まず第2章で退職届の要否を確認し、第3章と第4章で書き方とテンプレートを確認してください。提出時のマナーは第5章で説明します。各章は独立して読めるので、必要な部分だけ参照していただいても構いません。
役員の退職時に「退職届」は必要か?
概要
役員が退職する際は、一般に「辞表」を提出するケースが多いです。従業員が使う「退職届」と役員の「辞表」は慣習上の使い分けで、法律で明確に区別されているわけではありません。会社の規定や慣習で運用が分かれます。
法的な立場
法律上は、辞表や退職届の形式に厳格なルールはありません。取締役の任期が満了する場合は株主総会や取締役会の手続きで退任しますし、辞任する場合は本人の意思表示(書面や口頭)で成立することが多いです。
どちらを出すかの判断ポイント
- 就業規則・定款・取締役会規程を確認する。
- 代表権のある役員は書面での手続きが求められることがある。
- 会社の慣習(中小企業は退職届を求める場合も)を尊重する。
実務的な対応例
迷ったら総務・法務・社長に事前確認してください。形式を問われない場合は辞表で問題ありません。念のためコピーを残し、退任日や意思表示の日時を明確にしておくと後のトラブルを防げます。
まとめの代わりの一言
会社のルールに従うことが最優先です。疑問があれば事前に確認してください。
役員退職届・辞表の基本的な書き方
以下では、役員が退職届(辞表)を作る際の基本的な書き方をわかりやすく説明します。
表題
用紙の上部中央に「退職届」または「辞表」と記載します。役員は会社に対する辞任の意味合いが強いため、「辞表」を用いることが多いです。
宛名
宛名は会社の代表者や取締役会宛にします。例:
– 「代表取締役社長 〇〇殿」
– 「取締役会御中」
敬称は「殿」や「様」が一般的です。
書き出し
冒頭には謙譲の意を示す語を入れます。例:「私儀」「私事」。短く丁寧に始めます。
本文の書き方(例文)
簡潔に退職の意思と日付を記します。例:
「私儀、一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもって辞任いたします。」
役職名を明記する場合は「取締役を辞任いたします」などと続けます。
日付・署名・捺印
文末に退職日を明記し、署名欄に所属と氏名を書きます。提出日を右上に記すことが多く、氏名の横に捺印をしてください(実印や会社規程に従った印鑑)。
書くときのポイント
- 理由は「一身上の都合」など簡潔に。詳細な事情は別途口頭で伝えます。
- 敬語を使い、簡潔にまとめます。
- 事前に会社の規程や株主総会・取締役会での手続きが必要か確認してください。
役員退職届(辞表)テンプレート・記載例
概要
縦書き・横書きどちらでも使えます。縦書きは漢数字、横書きは算用数字を用いると慣例に沿います。印章(または署名)は忘れずに押してください。
縦書きテンプレート(例)
辞表
私儀
このたび一身上の都合により、令和〇年〇月〇日をもちまして役員を辞任いたしますのでここにお届け申し上げます。
令和〇年〇月〇日
(所属・役職)
(氏名) 印
株式会社〇〇
代表取締役社長 〇〇 殿
横書きテンプレート(例)
辞表
私儀
このたび一身上の都合により、202X年X月X日をもちまして役員を辞任いたしますので、ここに届出いたします。
202X年X月X日
(所属・役職)
(氏名) 印
株式会社〇〇
代表取締役社長 〇〇 殿
記載例(記入例)
例:令和三年四月一日を辞任
辞表
私儀
このたび一身上の都合により、令和三年四月一日をもちまして役員を辞任いたしますのでここにお届け申し上げます。
令和三年四月一日
管理部長
山田太郎 印
株式会社例社
代表取締役社長 佐藤一郎 殿
注意点
・日付は正確に。縦書きは漢数字、横書きは算用数字が一般的です。
・退任理由は簡潔にし、詳細は別途口頭で説明するとよいです。
・印章は氏名の右下に押印します。
提出時の注意点・マナー
「辞意を固めたら早めに提出」
提出タイミング
退任の意思が固まったら、できるだけ早く退職届を提出します。早めに伝えることで、引継ぎ期間を確保できます。特に役員は業務の継続性が重要なので、1〜3カ月前を目安にすることが多いです(会社規定が優先です)。
提出方法
原則は直属の上司か取締役会へ直接手渡しします。遠隔地ややむを得ない場合は、書留郵便や社内規定に基づくメール提出でも受理されます。会社の定める手続きを必ず確認してください。
書式・会社規定への対応
社内フォーマットや押印の有無がある場合はそれに従います。独自の理由書を添える時は事実に基づいた簡潔な説明にとどめます。
会社都合退職の場合の記載
会社都合で退任する場合は、背景や事実関係を具体的に書く必要が出ることがあります。労務手続きや社会保険に関わるため、正確に記載してください。
引継ぎと連絡
引継ぎ計画を作り、重要業務や連絡先を明示します。関係者への報告順(取締役→管理職→担当者など)を考えて円滑に進めましょう。
控えの保管と受領確認
提出後は受領印や受信メールの保存を必ず行います。後のトラブルを避けるため、控えを手元に残してください。
マナー
感謝の言葉を添え、感情的な表現は避けます。円満退職を心がけることが、今後の信頼につながります。
役員退職と従業員退職届の違い
呼称の違い
従業員は一般に「退職届」や「退職願」を使います。役員は「辞表」や「辞任届」と呼ぶことが多いです。呼称により書式や提出先が変わる場合があります。
提出先の違い
従業員は通常、会社の代表者や人事部に提出します。一方、役員は取締役会宛や代表取締役宛に提出することが多く、会議での承認が必要になることがあります。
記載内容・理由の違い
従業員は「一身上の都合」と簡潔に記すことが一般的です。役員は「辞任」と明記し、必要に応じて任期途中であればその旨や理由を添える場合があります。
手続き上の違い
役員の退任は登記手続きや取締役会・株主総会の決議が関係することがあります。従業員の退職ではこのような法人登記は不要です。
給与・保険・引継ぎの違い
役員報酬や社内の役割分担に関する調整が必要です。社会保険の扱いは、役員か従業員かで異なる場合があるため、確認が必要です。引継ぎ範囲も経営判断に関わる点が増えます。
具体例
- 従業員: 人事部に「退職届(一身上の都合)」を提出
- 役員: 取締役会に「辞任届(任期途中のため登記が必要)」を提出
上記の違いを理解して、書き方や提出先、手続きを適切に選びましょう。
まとめ・よくある質問
まとめ
役員の退職については、原則として「辞表」を提出するのが一般的です。ただし、会社の規程や慣習によっては「退職届」を求められる場合もあります。規程がないときは、代表取締役宛の辞表(氏名・役職・退任日・簡単な理由・日付・署名または押印)を提出すれば問題ありません。会社都合の解任などは、理由を明確にするか、会社側からの解任通知で処理されることが多い点に注意してください。登記や取締役会の承認が必要な場合もあるため、社内ルールやタイミングを確認して対応しましょう。
よくある質問(Q&A)
Q1: 役員でも退職届は必須ですか?
A1: 原則は辞表ですが、会社が退職届を求めれば従ってください。どちらでも形式を整えれば受理されます。
Q2: 提出先は誰ですか?
A2: 基本は代表取締役宛です。取締役会がある会社では取締役会で扱われることもあります。
Q3: 退任理由は詳しく書く必要がありますか?
A3: 自発的な退任は簡潔で構いません。会社都合や解任の場合は理由を明示するか、会社側の通知で示されることが多いです。
Q4: 書式に注意点はありますか?
A4: 氏名・役職・退任日・宛先・日付・署名(押印)を明記してください。登記や議事録用にコピーを保存しましょう。
Q5: 提出のタイミングはいつがよいですか?
A5: 登記や取締役会の日程に合わせて早めに調整すると安心です。事前に代表や総務と相談してください。
Q6: 法的手続きは必要ですか?
A6: 代表交代や登記が関わる場合、登記手続きや議事録作成が必要です。社内担当者や司法書士に確認してください。
分からない点があれば、会社の就業規則や法務担当に相談すると安心です。必要であれば、辞表・退職届の文例を用意します。
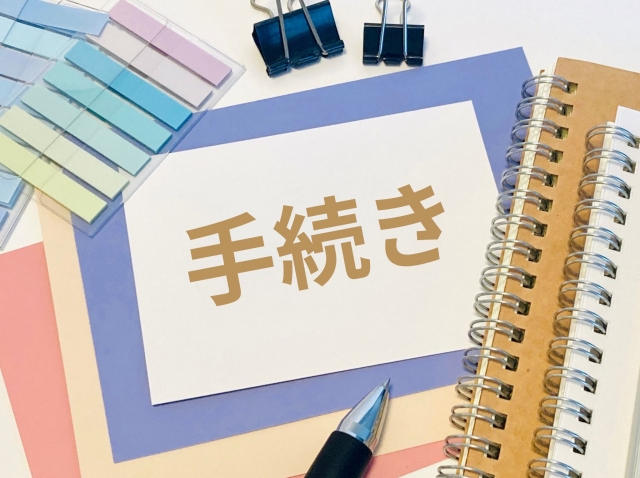









コメント