はじめに
この記事の目的
この章では、退職予告と解雇予告についての全体像をやさしく紹介します。法律の基本から実務で困りやすい点まで、順を追って理解できるように構成しました。これから退職や解雇に関わる手続きを控えている方、職場で相談を受ける立場の方に役立つ内容です。
誰に向けた記事か
- 自分で退職を考えている従業員
- 解雇の可能性がある従業員
- 人事や管理職など、手続きを担当する会社の方
具体例を交えながら説明しますので、法律に詳しくない方でも読み進められます。
本記事で学べること
- 退職予告と解雇予告の違い
- 従業員側・会社側それぞれのルールと注意点
- 実務での手続きの流れと対応のコツ
章ごとにポイントをまとめ、実際に使える知識を提供します。
読み方のポイント
まずは第2章で基本を把握してください。その後、ご自身の状況に合わせて該当章を参照すると理解が深まります。専門用語は最小限にして、例を挟みながら説明しますので、気軽に読み進めてください。
退職予告とは何か?
退職予告の基本
退職予告とは、従業員が退職する場合や会社が解雇する場合に、あらかじめその意思や事実を相手に伝えることを指します。言い方を変えれば「いつ会社を離れるか」「いつ従業員を離職させるか」を事前に知らせる仕組みです。退職(従業員側)と解雇(会社側)で扱いが異なります。
なぜ必要か
予告があることで、会社は後任の手配や業務の引継ぎを計画できます。従業員も退職後の手続きや生活設計を整えやすくなります。職場の混乱を避け、トラブルを防ぐ役割を果たします。
伝え方の例と実務上の注意
伝え方は口頭でも書面でも可能ですが、書面で残すと後の誤解を防げます。退職届やメール、記録に残る形が安心です。口頭だけで済ませると、退職日や引継ぎ内容で争いになることがあります。
簡単な事例
- 例1:社員Aは上司に1か月後に辞めると口頭で伝えたが、書面で確認しておらず退職日で揉めた。書面にしておけば回避できた事例です。
- 例2:会社Bが従業員に退職の予告を出して引継ぎ期間を確保し、業務が滞らなかった。
次章で、従業員側・会社側それぞれの法律上のルールを具体的に説明します。
退職予告(従業員側)の法律上のルール
ここでは従業員が会社に退職の意思を伝えるときの法律上の基本ルールを、分かりやすく説明します。
無期雇用(正社員など)
民法627条により、退職の意思を会社に伝えてから2週間経過すると退職が成立します。労働基準法に同様の規定はありません。2週間は「意思表示を行った日の翌日」から数え、休日も含めます。例えば4月1日に退職を伝えた場合、4月2日を1日目として数え、4月15日が成立日になります。
実務では口頭でも退職は可能ですが、誤解を避けるため書面(メールや退職届)で伝え、受領記録を残すことをおすすめします。
就業規則や会社のルール
就業規則で「1か月前に申し出」と定める会社はあります。原則として2週間以上の一方的な長期義務を課す定めは無効となる可能性がありますが、業務運営上の合理性が認められれば1か月程度の規定は有効と判断されることもあります。就業規則や雇用契約を必ず確認してください。
有期雇用(契約社員など)
契約期間が定められている場合、原則として期間満了まで退職できません。ただし本人の健康問題や事情の変更など「やむを得ない事由」があれば契約途中でも退職できます。具体性が重要で、事由や経過により判断が分かれるため、事前に会社と話し合うか、必要なら専門家に相談してください。
実務上の注意点
退職日や引継ぎの合意、未消化の有給休暇や最終給与の扱いなどはトラブルになりやすい点です。退職の意思表示は書面で行い、就業規則を確認し、必要なら人事と調整してください。
解雇予告(会社側)の法律上のルール
概要
会社が従業員を解雇する場合、労働基準法第20条により原則として「少なくとも30日前」に解雇を予告する必要があります。予告をせずに即時に解雇する場合は、労働者に代わって30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません(解雇予告手当)。
予告期間と手当の扱い
- 30日前に予告すれば手当の支払いは不要です。
- 30日未満の予告しかできない場合は、不足日数分の平均賃金を支払うことで足りません。具体的には、例えば20日前の予告なら不足は10日分なので、10日分の平均賃金を手当として支払います。
- 予告が全くなければ30日分の平均賃金を支払います。これが「解雇予告手当」です。
日数の数え方
予告日数は「予告した日の翌日から」数えます。土日・祝日を問わず暦日で30日を数えます。つまり稼働日でなくカレンダーの日数で計算します。
通知方法と書面交付の重要性
口頭での通知も可能ですが、解雇は労使間で争いになりやすいため、理由と解雇日を明記した書面(解雇予告通知書)を交付することを強くおすすめします。書面があれば後のトラブルで事実関係を確認しやすくなります。
具体例
月給30万円の従業員を即日解雇する場合、30日分の平均賃金に相当する約30万円を解雇予告手当として支払います。20日前に通知した場合は10日分、約1/3にあたる金額を支払うことになります。
注意点(簡単に)
- 解雇理由の正当性は別問題で、手当の支払いがあっても不当解雇の争いは生じ得ます。
- 例外や細かい計算方法はケースによって異なるため、実務では専門家に相談してください。
退職予告・解雇予告の例外と注意点
労災・産前産後休業などの保護
労働者が労災で療養中の場合や、産前産後休業中、その後30日間は原則として解雇できません。これは体調や出産による保護を目的としています。たとえば、業務上のけがで休んでいる間に会社が一方的に解雇を通告した場合、その解雇は無効となることが多いです。
就業規則と会社ルールを確認する
会社の就業規則で「退職の申告時期」を定めていることが多く、法律の最低予告に上乗せするルールもあります。円満退職を希望するなら、在籍中に就業規則を確認し、上司や人事と期日をすり合わせましょう。例:会社が「退職3か月前の申告」を求める場合、これに従えばトラブルが避けやすくなります。
予告期間を守らないとどうなるか
従業員が法定の予告期間を守らずに退職した場合、会社は実際の損害を主張して損害賠償を求めることがあります。一方、会社が予告をせずに解雇した場合は、解雇予告手当(平均賃金の30日分を支払うなど)を支払う義務が生じます。ただし、賠償の可否や金額は事情や証拠で左右されます。
即時解雇や特別なケース
業務上の重大な背信行為(横領や重大な発覚した不正行為)などがあると、即時解雇(懲戒解雇)になることがあります。これも証拠が重要で、軽いトラブルで即時解雇を乱用すると会社側が不利になります。
トラブルを避けるための実務ポイント
- 退職・解雇の意思表示はできるだけ書面やメールで残す。日付も明記する。
- 会社ルールと法定ルールの両方を確認する。就業規則の写しを入手する。
- 争いになりそうなら早めに労働基準監督署や社労士、弁護士に相談する。
これらを守ることで、不要なトラブルを避けやすくなります。
退職・解雇手続きの流れと実務ポイント
1)手続きの一般的な流れ
・従業員が退職を希望する場合、まずは口頭や退職届で意思を伝えます。民法上は意思表示から2週間後が最短退職日ですが、就業規則や業務引継ぎを考慮して余裕を持つのが望ましいです。
・会社が解雇する場合は、解雇理由を確認し、解雇予告通知書を交付します。法定の30日以上の予告をするか、30日分の解雇予告手当を支払います。
2)従業員側の実務ポイント
・退職届は日付と退職希望日、署名を明記します。口頭だけでなく書面で残すと後のトラブルを防げます。業務引継書を作成し、引継ぎ内容と期限を明示してください。
3)会社側の実務ポイント
・解雇の際は理由と日付を明確にして書面で通知します。解雇に正当な理由がなければ無効になる恐れがあります。懲戒解雇など厳しい処分は事前に社内手続きを踏み、記録を残します。
4)即日退職・即日解雇の扱い
・正当な理由がない即日退職は契約違反と見なされることがあります。即日解雇も原則禁止です。やむを得ない事情がある場合は、双方で書面を交わすなどしてリスクを下げてください。
5)書面と記録の管理
・退職届、解雇予告通知、引継書、面談記録などは保存しておきます。将来の労使紛争を防ぐために、日付と署名を必ず残してください。
まとめ・よくある質問
まとめ
- 「退職予告」と「解雇予告」は意味と手続きが異なります。退職は労働者から会社へ伝えます。原則は2週間前予告(民法)です。解雇は会社から労働者へ伝えます。原則は30日前予告か30日分の手当支給(労働基準法)です。
- 会社・従業員ともに、法定の手続きを守ることがトラブルを防ぐポイントです。就業規則や雇用契約の規定を必ず確認してください。
- 口頭でも効力はありますが、書面やメールで記録を残すと安心です。
よくある質問(Q&A)
Q1: 退職はいつ伝えればよいですか?
A1: 原則は2週間前です。会社の就業規則や雇用契約で長い期間が定められている場合はそちらが優先します。
Q2: 退職意思は書面で出す必要がありますか?
A2: 法律上は口頭でも可能です。証拠として書面やメールで届け出ることをおすすめします。
Q3: 会社が30日前に解雇予告をしなかったら?
A3: 会社は30日分の平均賃金を支払う義務があります(解雇予告手当)。不当解雇に当たる場合は労働基準監督署や専門家に相談してください。
Q4: 退職を会社が受理しないと言う場合は?
A4: 会社が受理を拒むことは実務上ありますが、退職の意思表示が届いていれば効力は生じます。記録を残し、必要なら第三者に相談してください。
Q5: 有給は退職時に消化できますか?
A5: 原則として取得できますが、業務の都合で会社と調整が必要です。就業規則を確認してください。
Q6: トラブルを避けるためのポイントは?
A6: 就業規則・契約内容の確認、退職届の写しやメール保存、相手と話し合いで合意を得ること。解決が難しい場合は労働相談窓口や弁護士に相談してください。
不明点があれば、具体的な状況(就業規則の条文や契約内容など)を教えてください。より詳しくお手伝いします。
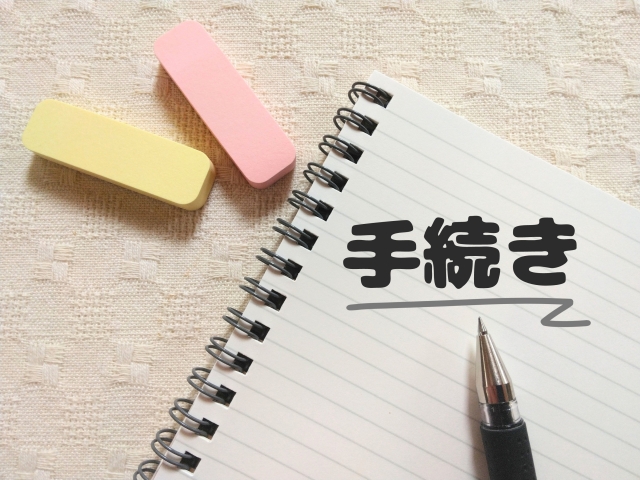









コメント