はじめに
本資料の目的
本資料は、退職予告期間に関する法的ルールと重要判例を分かりやすくまとめたものです。民法627条に基づく基本的な考え方や、実務で問題になりやすい点を整理しています。具体例を交えて説明するので、法律に詳しくない方でも理解しやすく作っています。
対象と範囲
対象は、労働者・使用者・人事担当者など実務で退職手続きに関わる方です。第2章以降で、民法627条の基本ルール、特殊な報酬体系での扱い、代表的判例である高野メリヤス事件、就業規則との関係、厚生労働省の見解、有期雇用や解雇予告との違い、予告違反時の責任まで順に解説します。
読み方のポイント
事例を優先して説明しますので、実務で直面するケースに当てはめて読み進めてください。条文や判例の趣旨を示した上で、日常の対応に役立つポイントを提示します。簡潔にまとめますので、必要な章を順にお読みください。
退職予告期間とは何か
定義
退職予告期間とは、労働者が会社に退職の意思を伝えるべき期間です。民法627条1項により原則として2週間前に予告することが求められます。労使双方が円滑に引継ぎや人員調整を行うための仕組みです。
法的な位置づけ
法律上、予告は労働者側の義務とされます。会社に到達した時点で期間が起算しますので、口頭より書面やメールで記録を残すと後のトラブルを防げます。
具体例
例えば4月30日退職を希望する場合、少なくとも4月16日までに予告します。期日直前に伝えた場合、会社が対応できないことがあります。
注意点と実務的アドバイス
就業規則や労使協定で別の取り決めがあることがあります。その場合は職場のルールに合わせる必要があります。急な事情で即時退職が必要なときは事情を説明し、書面で合意を得ると安心です。早めに伝え、記録を残すことをお勧めします。
民法627条1項が定める基本ルール
原則
民法627条1項は、期間の定めのない雇用契約(無期契約)について、当事者が予告を行うことで契約を終了できることを定めています。一般に、労働者が正社員など無期雇用を一方的に辞める場合、少なくとも2週間前の予告が「相当」として扱われます。
誰が対象か
対象は期間の定めがない雇用契約の当事者です。正社員や無期雇用のパートタイム労働者などが該当します。契約期間が定められた有期契約は原則別扱いです(別章で解説します)。
予告の方法と起算点
予告は口頭でも書面でも可能です。ただし後で争いにならないよう書面やメールで残すことをおすすめします。予告期間は通知が相手に到達した日から数えます。例えば、1月1日に退職の意思を対面で伝えた場合、その日から2週間経過した日が退職日になります。
具体例
- 例1:4月1日に「2週間後に退職します」と伝えた→4月15日が退職日になります。
- 例2:会社の承諾が得られず即日退職を希望する場合、会社の同意がないと原則として予告義務を果たしていない扱いになります。会社は損害賠償を主張することがありますが、実務上は双方で調整されることが多いです。
注意点
就業規則や雇用契約書に別の定めがある場合はその内容を確認してください。労働基準法上の解雇予告(使用者側の義務)とは扱いが異なります。同じ用語でも意味が変わるため混同しないでください。
特殊な報酬体系における3ヶ月前予告
背景
民法627条3項は、報酬を6か月以上の期間で定める場合(例:年俸制や半年ごとの固定支給)に、退職の申入れを3か月前に行うことを定めています。長期の報酬体系は安定性を前提にしているため、より長い予告期間を求める趣旨です。
適用の仕方
一方で、民法627条1項の2週間(14日)予告が基本ルールです。会社や契約の実務では、この一般ルールが優先的に運用されることが多い点に注意してください。つまり、給与体系が特殊でない場合は2週間で済むことが一般的です。
具体例
- 年俸制で1年分をまとめて評価・支給する契約がある場合は、3か月前予告が問題となる可能性があります。
- 月給制の通常雇用では、まず2週間の予告を想定します。
実務上の注意点
就業規則や雇用契約書を必ず確認してください。どちらの規定が優先されるかで扱いが変わります。あいまいな場合は会社に書面で確認し、争いが生じたら労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。
高野メリヤス事件—判例の重要性
事案の概要
東京地裁昭和51年10月29日判決(高野メリヤス事件)は、会社が就業規則で1か月前や6か月前の退職願提出を定めていた事案です。労働者は3か月前に退職を申し入れ、退職金を請求しました。争点は、就業規則の定めと民法627条の退職予告期間の関係でした。
裁判所の判断のポイント
裁判所は、実情や合意関係を重視して判断しました。就業規則で長期の提出期間を定めても、それが一律に労働者の権利を奪うものとしては認められない点を示しました。
判例の重要性
この判例は、労働者の退職意思と会社側の運営上の必要を両面から調整する考え方を示します。就業規則のみで一方的に退職の自由を制約できないことを確認した意義があります。
実務上の注意点
企業側は就業規則の運用を丁寧に説明し、合意や個別の事情を考慮する必要があります。労働者は退職時に合意内容を文書で残すと後の争いを避けやすくなります。
高野メリヤス事件の判決内容
事案の概要
会社の就業規則が労働者の退職予告期間を2週間より長く定めていました。裁判で争点となったのは、就業規則による延長が民法627条の労働者の解約の自由を制限するかどうかです。
裁判所の判断
裁判所は、民法627条の予告期間を使用者有利に延長することは認められないと判断しました。裁判所は労働者の解約の自由と法の保護を重視し、就業規則で2週間を超える予告期間を一方的に定めることは無効としました。
実務上の意味合い
この判決により、企業は就業規則だけで労働者の退職自由を狭めることができません。就業規則の見直しや、個別の合意を得る際の丁寧な対応が求められます。必要であれば労働相談窓口や弁護士に相談することをお勧めします。
就業規則と民法の関係性
裁判所の判断
裁判所は、就業規則は民法627条に反しない範囲でのみ有効だと判断しました。具体的には、退職の申入れを退職日の6ヶ月前とする規定については、そのまま全部有効とは認めず、労働者の解約の自由を著しく制約する部分は無効としました。
具体例で見ると
例えば、会社が「退職は6ヶ月前に申請すること」と規定していても、裁判所はその効力を6ヶ月分まるごと認めず、労働者が比較的短期間で退職できるように、法的に許容される範囲(判例では2週間を超えない範囲)までに限定しました。
退職許可制の扱い
また、退職を会社の許可制とする規定も問題視されました。裁判所は、許可がなければ退職できない仕組みは労働者の解約の自由を実質的に奪うとして無効と判断しています。
実務上の注意点
就業規則を作る側は、実効性を確保しつつも民法627条の趣旨に抵触しないよう配慮する必要があります。労働者側は、長期の予告や許可制を理由に不利益を受けた場合、記録を残して相談窓口や専門家に相談するとよいでしょう。
民法627条の強行規定性
民法627条は「退職の予告は少なくとも2週間前にする」と定めています。下級審の裁判例は、この規定を強行規定(当事者間で短縮できないルール)とみなし、労働者の退職申出には原則として2週間の予告期間が必要だと明確にしています。
具体的には、就業規則や誓約書で「退職には1か月の予告が必要」などと定めしても、その部分は民法627条に抵触する疑いが出ます。裁判例は、労働者に不利に働く短縮や追加の義務を一方的に課す規定の効力を問題視しています。
例を挙げると、会社が就業規則で「退職は1か月前に申し出ること」としていた場合、労働者が2週間前に退職を申し出すと、裁判所はその退職を有効と判断する可能性があります。逆に会社側が2週間未満での退職を理由に損害賠償を請求するのは難しくなります。
実務的には、会社側は予告期間に関する規定を見直し、労働者は退職届を出す際に日付を明確にしておくと安心です。問題が起きたときは、労基署や労働関係の専門家に相談するとよいでしょう。
厚生労働省の公式見解
概要
厚生労働省は、裁判例の方向性に沿って、退職予告期間として「2週間を超える定め」は原則無効とする見解を示しています。行政と司法が一致することで、労働者の退職の自由が強く保護されています。
行政の対応例
厚生労働省は通達やQ&Aで労働局に指示を出し、企業の就業規則に過度な予告期間があれば無効扱いになると説明しています。労働者は最寄りの労働局や相談窓口で助言を受けられます。
具体的な場面
たとえば会社が「退職は1か月前に申し出ること」と規則に定めている場合、行政見解ではその規定は無効で、労働者は2週間で退職できるとされています。会社が拒むときは行政相談や和解の仲介が利用できます。損害賠償の主張は個別判断になります。
事業主への助言
事業主は就業規則を見直し、労働者に分かりやすく周知してください。トラブルを避けるため、予告期間の運用は行政見解に合わせることが勧められます。
有期労働契約との違い
概要
有期労働契約は、契約で定めた期間が満了すると契約が終了します。期間途中に一方的に辞めることは原則できません。やむを得ない事由がある場合や、双方が合意した場合に限り中途解約が認められます。
主な違いとポイント
- 期間の効力:有期は契約で期間が決まるため、満了まで働く義務があります。無期や一般の退職規定とは扱いが異なります。
- 途中退職の扱い:労働者側が期間途中で辞める場合、原則として会社の承諾が必要です。例えば重い病気や家族の事情など“やむを得ない事由”があるときは例外的に認められることがあります。
- 就業規則と法令の優先:会社の規則より民法や労働基準法のほうが優先され、労働者の基本的権利は法令で守られます。就業規則に“期間途中退職は不可”とあっても、法に反する扱いは無効です。
実務上の対応例
- 退職を希望する場合は、まず会社と話し合い合意書を作成します。合意が得られないときは、やむを得ない事情を証明できれば裁判で認められる可能性もあります。
- 会社側が契約を途中で終了させる場合は、正当な理由や解雇手続きが必要です。無断で契約を終了すると労働者に損害賠償責任が生じることがあります。
注意点
有期契約でも更新や雇止めのルールが別にあるため、契約書と就業規則をよく確認し、不明な点は労基署や専門家に相談してください。
解雇予告期間との相違
概要
退職予告期間は労働者が自ら退職するときに用いる予告で、原則として2週間前の通知で足ります(民法627条)。一方、解雇予告期間は会社が労働者を解雇するときのルールで、原則30日前の予告が必要です。解雇せずすぐに職を離れさせる場合、使用者は30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払います。
主な違い(分かりやすく)
- 誰が使うか:退職予告=労働者、解雇予告=使用者。
- 期間の長さ:退職は原則14日、解雇は原則30日。
- 金銭的対応:退職は通常支払いなし、解雇で予告しない場合は30日分の手当を支払う義務が生じます。
具体例
- 例1:社員Aが4月30日付で退職したいとし、4月16日に会社に伝えれば足ります。
- 例2:会社が社員Bを即日解雇する場合、会社は30日分の平均賃金をBに支払う必要があります。
注意点
就業規則や労働契約で、双方が合意すれば実務上の取り決めを変えることがあります。ただし、解雇予告手当は労働者保護の観点から重要な制度ですから、使用者は簡単に免れることはできません。疑問がある場合は、会社の総務や労務担当に確認してください。
予告期間を守らない場合の法的責任
事案の概要
大阪高裁昭和58年4月12日判決では、就業規則に定めた退職予告期間を守らず退職した従業員に対し、会社が退職金の不支給を認められました。会社側は規則違反で実務上の損害が生じたと主張しました。
裁判所の判断のポイント
裁判所は、単に予告が短いというだけで自動的に退職金を没収できるとしませんでした。会社側が具体的な損害を示し、その不支給が相当であると認められた特別な事情があった点を評価しました。
一般的な法的枠組み
民法627条は原則として退職の2週間前予告を定めます。通常はこのルールが優先します。会社の就業規則で長い予告期間を定めることは可能ですが、それを理由に賃金(退職金を含む)を一方的に差し引くには限界があります。損害賠償を求める場合、会社は実際の損害と因果関係を立証する必要があります。
実務上の注意点(企業側)
・就業規則は明確にし、従業員に周知してください。
・不支給を検討する際は、具体的な損害額の算定と証拠を揃えてください。
・賃金に当たる退職金の一方的なカットは労基法との関係で問題になります。弁護士に相談することを勧めます。
従業員への助言
退職時は就業規則を確認し、可能な限り規則どおりに予告してください。もし退職金を不支給にされた場合は、まず会社に理由と根拠を求め、納得できなければ労働基準監督署や弁護士に相談してください。裁判例は例外的判断である点を忘れないでください。
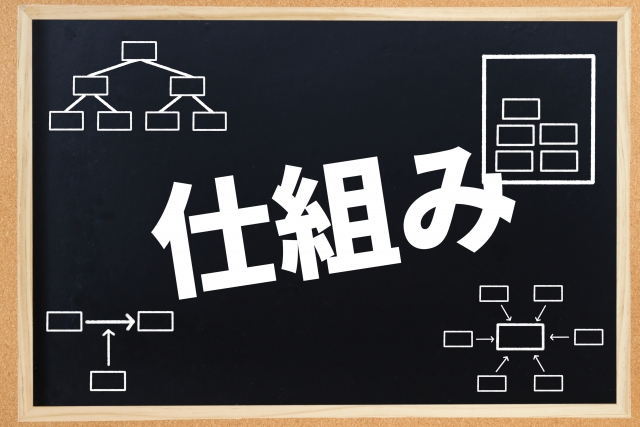








コメント